| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
俺たちで文豪ストレイドッグスやってみた。
作者:絶炎with八咫烏
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動第5話「汝に幸あれ」
前書き
今回以降は執筆は八代明日華さんか担当しております
健は袋小路を形成する塀に背を預け、『そいつ』が来るのを待っていた。足音や気配は覚えている。近づけばすぐわかる。それゆえの自然体。リラックスした体勢。
だがそれは、事情を知らない人間から見れば、相手を馬鹿にしているのか、あるいは余裕を持ちすぎているようにも見える。
「……なんですか、その態度は」
『彼』は不機嫌そうに、そう問う。俺を愚弄するつもりなのか、と。敵意を持っている存在からすれば、健の姿勢は明らかな挑発と受け取ることもできるからだ。
だが、健にはもちろんそんな意図はない。脱力したような姿勢をとっているのは、そうする方が過ごしやすいからだし、何より彼の側からすれば、旧知の間柄である人物との再会は、できるだけ自然体で切り出したかった。
「久しぶりだね、祐介君。また会えて嬉しいよ」
「俺は全く嬉しくありません。……できれば——もう二度と会いたくはなかった」
健が身を潜めていた裏路地に姿を現したのは、一人の青年だった。暗い茶色の髪をした、テーラージャケットを羽織った男。背が高い。首からは、リングネックレスをかけている。
健とはまた違ったベクトルで女性受けのしそうな端正な顔立ちを、今は憎悪と嫌悪に歪めて、彼は言う。どうして俺を呼んだのか、と。健は笑う。君の顔が見たくなっただけさ、と。祐介、と呼ばれた茶髪の青年は、はっ、と嘲笑って、その言葉、女性に言われたかったかな、と呟いた。
しかし直後、真剣な表情に戻ると、青年——黒木祐介は、健に向かってこう問うた。
「——それで? 聞きたい事、っていうのは、なんですか?」
バレてた? とは聞かない。そもそも彼に自分の目的が筒抜けなことなどお見通しだ。それくらいには互いのことをよく知っているし、相手が考えそうな行動に対する予測も建てられる。
だから健も、最初からその話題であったかのように、答えるだけ。
「単純なことだよ。君たち——なんで、絵里さんのことを追ってるの?」
顔には、笑顔を張り付けたまま。しかし、声はある種極寒の冷たさを孕んで。
道化師 だ。詐欺師 だ。分かる者ならそう分かる。分からぬものなら騙される。健の話術。幻惑するようなそれは、今までも、多くの人間から有益な情報を得てきた。
だが。
「それを教えることは、僕にはできませんね」
「あらま」
祐介は笑う。知っているからだ。健と会話してはならないと。彼から情報を抜き出されないためには、彼と会話をするということ自体を避ける必要があると。誰よりも知っているのはこの男だ。健が祐介の手の内を知り尽くしているように、祐介もまた、健の手の内を知り尽くしているのだ。
互い互いが、ある種の天敵のようなモノ。それが、この二人の関係性。
健は表情を崩す。不機嫌そうに。しかしどこか楽しそうに。祐介もまた、体勢を変える。次に何が来るか、やはり、『知っている』から。
「ちぇっ、詰まんないの」
——ガチャン、ダン。
軽い音。静かな銃声。サプレッサー付きの特注拳銃は、この狭い裏路地の中でもしっかりと音を殺してくれる。
健が銃を抜き放っていた。手元を見ないでのクイックドロウ。並大抵の人間ができることではない。それはその技術——いうなれば『殺しの技』を、徹底的に、いっそ反射的になるまでと言えるほどの期間、己の身に叩き込み続けた者だけが至れる境地。常人に対応することなど、不可能と言っていい。
しかし。
「俺からすれば、逆に不思議で仕方がないですよ。よりにもよって貴方が、あの女を守ろうとするなんて」
ほぼ無音に近い状態で、神速を以て放たれた、銃弾は、いたって自然な動作で祐介に避けられた。彼が不思議そうに小首をかしげるのとほぼ同時に、彼の顔の真横を銃弾がかすめたのだ。青年には、一切の被害なし。損害は、健が銃弾を一発、喪ったということだけ。
「……へぇ。マフィアからは、守っているように見えるのかい」
「ええ、まぁ」
祐介は笑う。健も笑う。どちらも、心の中では全く笑っていない。
「僕はただ知りたいだけさ。いまだにはっきりとは見えない、君たちの目的ってやつをね」
「『好奇心は猫を殺す』、って言葉、知ってますか」
「知ってるさ、勿論」
「俺は貴方の命を心配している」
「僕としては、君の命の方が心配なんだけど——ね‼」
再び、撃つ。銃弾は最初から込められている。セミオートの拳銃は、最小限の動きで弾倉を再装填できる。そのための技術が、健の腕にはしみついているのだ。
そしてそれを回避するための技術も、とるべき行動も、何も知らないのにも関わらず。

「……ちっ、やっぱりそれだけは好きになれないなぁ。君の異能」
「そうですか」
笑顔のまま、健は呻く。祐介は、表情を崩さない。健の背中に流れる、一筋の冷や汗。
祐介は、やはりごく自然に、ゆるりと、しかし確かに、銃撃を避けるのだ。
——幸運というものは、誰しもある程度は備えている。それが例えば小人族の黄金 から得られた偽りのものであれ何であれ、幸運というものは、宿り手にある程度の繁栄を保証する。
そして同時に幸運は、宿り手に努力を強要する。幸運は努力した者のところにのみやってくる、とはよく言ったもので、運を引き寄せるためにはそれなりのお膳立てが必要なものだ。
黒木祐介の異能は、その『お膳立て』を超越する。
彼の持つ異能は、厳密には現代でいうところの『異能』ではない。もっと古い、それこそ魔眼だとか、超能力だとか、そういう『体質』の類の一種だ。
名を、『幸運EX』——ただそこにいるだけで、運命に愛される体質。金銭、職業、色恋、籤運。凡そありとあらゆる『運』が絡む概念に関して、彼は本来ならば強要される『努力』の一切を無視して、誰もがうらやむ最上の結果を手に入れることができる。それもある程度のコントロールが可能であり、『最上』の形は彼が自由自在に変えることができるのだ。
例えば——絶対に当たるはずの銃弾を、万に一つの確率で、『偶然にも』避けることができるなら。
彼は、『絶対に』銃弾を避けるのだ。
何の技術も、努力もなしに。
健の銃撃は止まない。だが、その悉くは祐介ではなく、背後のコンクリートを打ち抜いていく。
やがて終わりは必ず来る。マガジンから銃弾が吐き出され尽くし、遂にトリガーを引いてもかちっ、かちっ、という間の抜けた音が聞こえるのみとなった。健の表情が初めて崩れる。
「ちっ……」
「終わりですか? じゃぁ、ここで死んでください——」
すっ、と。
祐介が、健の目の前に現れる。縮地、と呼ばれる、特殊な走行方法——剣術や剣道などの、近接戦闘武術の達人だけが身に着けることを許された、距離を圧縮する足遣い。長い努力と鍛錬を以て得ることができるはずのその技術を、彼は『偶然にも』全く努力することなく使えるのだ。
顔が近づく。この距離から逆転する手段。無いわけではない。健の異能である『Moon Light Fantasy』を利用すれば、遠くまで逃げることは可能だろう。幸いにして今は月が出ている。能力発動のトリガーはそろっていた。だが、そのためには一瞬の隙が必要だし、その間隙は、この状況で生み出すことは不可能に近い——
「……裏切者」
「……え?」
しかし。祐介は、健に向かって、ナイフや銃を突きつける、あるいはその肉体で打つ、と言ったことをしたわけではなかった。
「殺したいのはやまやまですよ。でも俺にも、知りたいことはある……貴方が……いいや、あんたがどうしてユミナ様を裏切ったのかだ。そして、どうしてあのヒトがあんたを赦しているのかだ。それを知るまで、あんたを殺すことはできない——教えろ」
「——それこそ、『好奇心は猫を殺す』、だぜ」
次の瞬間には、健は能力を発動させていた。空間が歪む。祐介が端正な顔を歪ませ、舌打ちをするのが聞こえる。
「じゃあね」
月に夢見る猫が映る——そんな錯覚の中。景色が、切り替わる。
探偵社の二階、健達のプライベートスペースへと。
「……好奇心は、猫を殺す、ねぇ」
健は苦笑して、鞄の中へと手を突っ込む。くしゃり、という感触。この事務所を出たときには、入っていなかったものだ。
「不用意なことは言うもんじゃないよ、祐介君」
その手には、一部の書類が携えられていた。『古代機 開発依頼発注書』、と丁寧にも書いてあるそれは、先ほどの祐介が、やはり鞄の中に入れていたものだ。おそらくは紛失することを警戒して常に持ち歩いていたのだろうが、甘い。健の方が一手先を行っていた、ということだろう。健の『Moon Light Fantasy』は、何も歪められる空間が一か所だけとは言っていない。そもそも転移する先ともともと自分がいる場所、という二か所の空間を歪めるのだ。さらに広げることが可能だとしても、なんら不思議はない。
健は先ほどの転移のときに、同時に祐介からこの書類を奪ってきていたのだ。これでマフィアたちが絵里を追う理由はほぼ確定した。あのスケッチブックに描いたモノを、現実のものとして顕現させる異能——あれと古代機を以て、何らかの現象を引き起こそうとしているに違いない。
だが、まだわからないことはある。何故絵里でなければならないのか。彼女がどうやらスケッチブック以外の場所に実体化する絵を描くことはできないらしい、ということは、注意深く観察すればすぐ分かる。そしてサイズは描いたモノと同寸——つまり、あまり大きなモノは創りだすことができないのだ。
そこから考えることができる、マフィアたちから見た絵里の『利用価値』は——
「健さん、どこに行ってたんだ」
「ん? ああ——ごめんごめん。集まってもらってたことを忘れてた」
思考が中断される。下手人は兵児だ。彼は無表情の中にも少しの不機嫌さをたたえながら、じっ、と健を見つめていた。
兵児だけではない。達也、絵里、かずのこの三人もまた、健のことを呆れたように見ている。
「それで。態々俺達を集めた理由は何なんだ?俺まで呼ぶなんて、何か重大なことなんだろ」
面倒くさがりの彼に相応しく、ほぼ全く表情を動かさずに、兵児は静かに問う。うんうん、と後ろでかずのこが頷くのが見える。「僕執筆したいんですけど」という顔だ。
これは変なことは言えないな……と、先ほどとはまたちょっと違った緊迫感を感じながら、健は笑った。持っていた書類を机の上に置き、皆の方を向く。
「うん、まぁ、大事なこと」
「勿体ぶらないで下さいよ。何なんです?」
達也が少しイラついた声で言う。これはまずい。彼を怒らせたらよくない。健は慌てて、
「単刀直入に言うと——絵里さんに、この探偵社に入ってもらおうと思ってね」
言った。ほう、へぇ、と言う声が上がる。
一番混乱しているのは、言われた本人——絵里の様だったが。
「え……えぇっ?」
「これはびっくりなのですー」
僕も驚き桃枝山椒枝、と妙なことを言いつつ、かずのこがお道化た。そしてそのままデスクチェアーにゆっくりと、謎の優雅な動作で座ると、特に何も入っていないグラスを口につけ、何かを飲むような動作をしてからこちらを見る。そして唐突に画風の違……キメた表情をとると、
「僕は大歓迎ですよ」
「それ言うためにその動作したの?」
「いやん、リッチ」
達也と兵児が反射的に突っ込みを入れる。ちなみに兵児は変わらず無表情、ついでに棒読みである。
「い、いや、そんなこと言ってる場合じゃなくて……っ!」
「じゃぁ決まりね」
「ちょ、ちょ―――ちょっと待ってください!」
わたわたと焦る絵里をよそに、健は笑顔で結論付ける。もちろん絵里は話題の終了を阻んだ。
「どうして急にそんなことを? それに、なんで私が……?」
眉根をよせて、不安そうに問う彼女。どうやらある種依頼者的立場でしかなかった自分が、唐突に『被依頼者』の側に入る、ということが不思議で仕方がないらしい。
健はんー、としばし考える。
「じゃぁさ、逆に聞くけど……絵里さんは、この先どうするつもりなの?」
「え……?」
「家に帰るのは無理なのは知ってるよね。それに今は僕たちが護衛してるけど、いつまでもこの状況が続くとは限らない。兵児君のおかげで前回、キョウヤの襲撃をはじき返すことができたけど、次もうまくいくとは限らない。兵児の『Smart Links』にも、召喚の限界はあるんだ。
逆に向こうには、まだ遭遇していない異能者がいるかもしれない。こちらの手札はほとんど見せているのに、向こうの全貌は把握できていないし。こないだそれで痛い目見てるでしょ」
絵里の脳裏に蘇るのは、小柄な黒髪の少年だ。狼のようなフードを被った彼は、人懐っこそうな笑顔と共に絵里に近づき、そして——
あの時のことを思い出すと、震えが走る。
「もちろん、護衛は続ける。けど、それにもいずれ限界がくる、ってことさ。こっちも仕事だ。お金はもらわないといけない。だけど、絵里さんにはそのお金にも限界がある——」
そうだ。
自分は、狙われているのだ。まっとうに働くことは赦されていない。護衛の人たちは、共に働くことはできまい。何より、同僚たちを危険にさらしてしまう——
ぞっ、と。
絵里の足元に、黒い穴が開いたような錯覚。虚無だ。無だ。何も見えない、底なしのヴォイド。このままなら、どこまででも引きずり込まれて——
「だからそのための考え、ってことですよ。そうでしょう、健さん」
達也のその一言で、はっ、と絵里は我に返る。彼を見れば、その真面目そうな顔をさらに真剣な表情で覆って、背の高い少年は言う。
「依頼者——ある種の『客』としてなら、報酬に限界が来た時点で俺たちは手を引かなくちゃいけない。たいして従業員——『仲間』としてなら、俺達にはそれを護るという義務がある。それは法律的にもそうだし、何より俺たちの信条がそうさせる。俺達よりもずっとずっと執念深くて、狡猾な異能マフィア達をしのぎ続けるためには、絵里さんに常に共に行動してもらわないといけない」
「なるほど、さすが達也。僕たちの頭脳。天才だね」
「いやいやまさかそこまで考えてなかったとか言いませんよね?」
「うん。言う」
「おかしい! 理不尽だ! 言い出しっぺがマトモに説得理由考えてないとか!!」
「……」
絵里は考える。
確かに、それは名案だ。それなら、自分の身を守りつつ、周りの人の心配もしなくていい。彼らが一人一人が予想もつかないほど強いことは知っている。自分が心配する必要がないほど。
だけど。
「でも、本当に私なんかが、いいんでしょうか。私がいる限り、みなさんに迷惑が——」
「そういうのはいいのいいの。仲間うちなら迷惑かけても当然よ」
「そうですよ~! ボクなんてプロになるまで何年兵児さんがカードゲームの世界大会で稼いできた大金をまるっと頂いてると思ってるんですか~!」
「ん……? おいちょっと待て。お前今妙な事——」
「えー、なんですか? すみません、耳にヒラメが入ってまして」
始まった茶番を呆然と見つめながら、絵里は内心で苦悶する。揺れ動く。迷惑をかけたくない。でも、この人たちになら、頼ってもいいのかもしれない、と。
その様子を、別の理由で逡巡しているのだと思ったのか、達也が後頭部をかきながら歯切れ悪く言う。
「まぁ、いきなりこんな胡散臭い探偵社に入れ、なんて言われても困りますよね」
「え……い、いえ。胡散臭いなんて、そんなことは──」
「まぁ胡散臭いのは仕方ないね。実際そうだし。だから、そうだなぁ……仮入社、もしくはアルバイトみたいな感じで。期限は、この事件が収拾するまで。どうかな?」
にこり、と。いつもの道化師のようなそれとは違う、柔らかい笑顔を浮かべて。
健が、右手を差し出す。
達也も。騒いでいたかずのこと兵児も。
「あ……」
知らず知らずのうちに、絵里の右手も、彼らの掌へと延びていた。
「よろしく、お願いします」
「うん、よろしくお願いされました」
「ようこそ、我らの探偵社へ」
「かずのこちゃんは絵里さんを歓迎しますよ~!」
「俺も面倒でないなら力になろう」
温かく自分を迎え入れてくれた彼らに、絵里の頬も緩む。ああ、これなら、きっと、大丈夫。
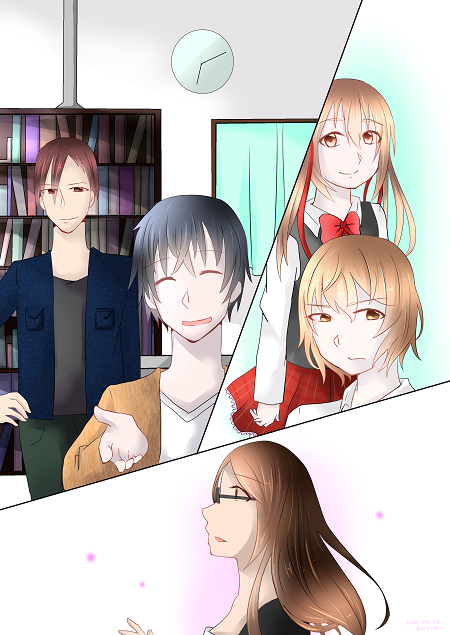
「じゃぁ、早速入社式と行こうか! たしか焼肉の機材をこないだ注文したはず——」
健が笑って、機材を探しに行こうと、一歩を踏み出した。
「そうですね。じゃぁ、ついでに退社式と行きましょうかぁ!」
「「「「──!?!?」」」」
その時だった。
歪む。空間が。それはある意味で健のそれと同じで、しかし根本的に違う能力。
健のそれは、空間を歪ませ『飛ぶ』技術。制約も多々ある代わりに、汎用性も高い。
たいして『それ』は、ただひたすら『繋げる』ことに特化した業 。汎用性を犠牲にした代わりに、「その目で実際の場所を見る」というただそれだけで、ありとあらゆる空間へと、自由自在に『扉を開く』。
異能名、『その扉の向こう側に』。
それを持っている人物は、一人だけ。
「みんな大好き、ろーがさんの登場だよ」
黒髪の少年が、立っていた。先ほどまでは誰もいなかったはずの、健達の背後。机の上——健が、祐介から奪い取った書類を置いていた、机の上だ。そこに、黒鉄狼牙が腰かけている。
にまにまと笑う彼の姿を見た瞬間、図られた——と、直感的に、健は悟った。同時に心の中で、何度も舌打ちをする。
祐介は、別に不用意に書類を持ち歩いていたわけではなかったのだ。健が彼の考えることをすべて把握できるのと同じように、彼もまた、健が考えることすべてを思いつく。
そして、決定的に二者を分けるのは——備わった、『幸運』だ。
祐介は、健の思い通りに動くことは無い。祐介の幸運が、健の思い通りに動かない未来、即ちは自分に有利な未来を引き寄せるからだ。
健は、祐介の思い通りに動く。なぜなら、祐介の幸運が、健が思い通りに動く未来を、つまりは自分に有利な未来を引き寄せるからだ。
完全に見透かされていたのだ。健が祐介から書類を奪うということは。
完全に予定されていたのだ。健が——すっかり、狼牙の能力の発動条件に関する考察を忘れているということは。
『その扉の向こう側に』は、「一度見た場所」をトリガーに、あらゆる場所と場所を繋げる力だ。だが、「場所」というのは、いったいどのような基準で選ばれているのか?
簡単だ——能力者の、主観である。
例えば。祐介が、書類をどこかの机の上に置いたとして。
その上に狼牙が立つとして。
——『書類の上という場所』を、『扉』を繋げる先の風景として、登録していたならば。
あの書類を健が奪い取り、そして机の上に置いた、という時点で、このプライベートルームは、彼の転移の範囲内……!
「やぁ……エース君」
背を伝う冷たい感触を必死で押さえつけながら、健は少年に呼びかける。彼はその名を聞いて露骨に顔をしかめた。
「その名で呼ぶな」
冷たい、氷のような。いや——獣が、冷酷に獲物を狙うような、目。それはその場にいる人間を。特に、戦いに慣れない絵里を凍り付かせるのには。十分だった。
「まぁいいです。そんなことより皆さんに残念なお知らせでーす!」
次の瞬間にはいつもの明るい笑顔に戻った狼牙は、直後、衝撃的な言葉を口にした。
「このビル、今、僕たちの方で完全に包囲させて貰ってまーす」
「……何っ……?」
窓の外を見る達也。彼の表情がこわばる。健にも分かる。なんというか、重圧。狼牙の言っていることは、真実だと、本能が告げている。
「達也、なんか解決方法ない?」
「無理です。完膚なきまでに囲まれてます」
珍しく、達也が即答でさじを投げる。
「なんだって、そいつはたいへんじゃぁないか!」
お道化て見せる健。
「はい、というわけで、健さんたちはおとなしく降伏しやがってくださいませませ~」
狼牙はにっこりと黒い笑みを浮かべる。ひっ、と、小さな悲鳴を上げる絵里。
「健さん……どうするつもりなんだ?」
兵児が問う。健はうーん、とうなると。
「うん、打つ手なし! 分かった、降伏しよう!」
両手を挙げて、たははー、と笑った。
「「「え?」」」
「え?」
探偵社の四人が驚いたように目をむき、健を見る。
そして誰より。
「……え?」
狼牙が、間抜けた声を上げた。
ページ上へ戻るだがそれは、事情を知らない人間から見れば、相手を馬鹿にしているのか、あるいは余裕を持ちすぎているようにも見える。
「……なんですか、その態度は」
『彼』は不機嫌そうに、そう問う。俺を愚弄するつもりなのか、と。敵意を持っている存在からすれば、健の姿勢は明らかな挑発と受け取ることもできるからだ。
だが、健にはもちろんそんな意図はない。脱力したような姿勢をとっているのは、そうする方が過ごしやすいからだし、何より彼の側からすれば、旧知の間柄である人物との再会は、できるだけ自然体で切り出したかった。
「久しぶりだね、祐介君。また会えて嬉しいよ」
「俺は全く嬉しくありません。……できれば——もう二度と会いたくはなかった」
健が身を潜めていた裏路地に姿を現したのは、一人の青年だった。暗い茶色の髪をした、テーラージャケットを羽織った男。背が高い。首からは、リングネックレスをかけている。
健とはまた違ったベクトルで女性受けのしそうな端正な顔立ちを、今は憎悪と嫌悪に歪めて、彼は言う。どうして俺を呼んだのか、と。健は笑う。君の顔が見たくなっただけさ、と。祐介、と呼ばれた茶髪の青年は、はっ、と嘲笑って、その言葉、女性に言われたかったかな、と呟いた。
しかし直後、真剣な表情に戻ると、青年——黒木祐介は、健に向かってこう問うた。
「——それで? 聞きたい事、っていうのは、なんですか?」
バレてた? とは聞かない。そもそも彼に自分の目的が筒抜けなことなどお見通しだ。それくらいには互いのことをよく知っているし、相手が考えそうな行動に対する予測も建てられる。
だから健も、最初からその話題であったかのように、答えるだけ。
「単純なことだよ。君たち——なんで、絵里さんのことを追ってるの?」
顔には、笑顔を張り付けたまま。しかし、声はある種極寒の冷たさを孕んで。
だが。
「それを教えることは、僕にはできませんね」
「あらま」
祐介は笑う。知っているからだ。健と会話してはならないと。彼から情報を抜き出されないためには、彼と会話をするということ自体を避ける必要があると。誰よりも知っているのはこの男だ。健が祐介の手の内を知り尽くしているように、祐介もまた、健の手の内を知り尽くしているのだ。
互い互いが、ある種の天敵のようなモノ。それが、この二人の関係性。
健は表情を崩す。不機嫌そうに。しかしどこか楽しそうに。祐介もまた、体勢を変える。次に何が来るか、やはり、『知っている』から。
「ちぇっ、詰まんないの」
——ガチャン、ダン。
軽い音。静かな銃声。サプレッサー付きの特注拳銃は、この狭い裏路地の中でもしっかりと音を殺してくれる。
健が銃を抜き放っていた。手元を見ないでのクイックドロウ。並大抵の人間ができることではない。それはその技術——いうなれば『殺しの技』を、徹底的に、いっそ反射的になるまでと言えるほどの期間、己の身に叩き込み続けた者だけが至れる境地。常人に対応することなど、不可能と言っていい。
しかし。
「俺からすれば、逆に不思議で仕方がないですよ。よりにもよって貴方が、あの女を守ろうとするなんて」
ほぼ無音に近い状態で、神速を以て放たれた、銃弾は、いたって自然な動作で祐介に避けられた。彼が不思議そうに小首をかしげるのとほぼ同時に、彼の顔の真横を銃弾がかすめたのだ。青年には、一切の被害なし。損害は、健が銃弾を一発、喪ったということだけ。
「……へぇ。マフィアからは、守っているように見えるのかい」
「ええ、まぁ」
祐介は笑う。健も笑う。どちらも、心の中では全く笑っていない。
「僕はただ知りたいだけさ。いまだにはっきりとは見えない、君たちの目的ってやつをね」
「『好奇心は猫を殺す』、って言葉、知ってますか」
「知ってるさ、勿論」
「俺は貴方の命を心配している」
「僕としては、君の命の方が心配なんだけど——ね‼」
再び、撃つ。銃弾は最初から込められている。セミオートの拳銃は、最小限の動きで弾倉を再装填できる。そのための技術が、健の腕にはしみついているのだ。
そしてそれを回避するための技術も、とるべき行動も、何も知らないのにも関わらず。

「……ちっ、やっぱりそれだけは好きになれないなぁ。君の異能」
「そうですか」
笑顔のまま、健は呻く。祐介は、表情を崩さない。健の背中に流れる、一筋の冷や汗。
祐介は、やはりごく自然に、ゆるりと、しかし確かに、銃撃を避けるのだ。
——幸運というものは、誰しもある程度は備えている。それが例えば
そして同時に幸運は、宿り手に努力を強要する。幸運は努力した者のところにのみやってくる、とはよく言ったもので、運を引き寄せるためにはそれなりのお膳立てが必要なものだ。
黒木祐介の異能は、その『お膳立て』を超越する。
彼の持つ異能は、厳密には現代でいうところの『異能』ではない。もっと古い、それこそ魔眼だとか、超能力だとか、そういう『体質』の類の一種だ。
名を、『幸運EX』——ただそこにいるだけで、運命に愛される体質。金銭、職業、色恋、籤運。凡そありとあらゆる『運』が絡む概念に関して、彼は本来ならば強要される『努力』の一切を無視して、誰もがうらやむ最上の結果を手に入れることができる。それもある程度のコントロールが可能であり、『最上』の形は彼が自由自在に変えることができるのだ。
例えば——絶対に当たるはずの銃弾を、万に一つの確率で、『偶然にも』避けることができるなら。
彼は、『絶対に』銃弾を避けるのだ。
何の技術も、努力もなしに。
健の銃撃は止まない。だが、その悉くは祐介ではなく、背後のコンクリートを打ち抜いていく。
やがて終わりは必ず来る。マガジンから銃弾が吐き出され尽くし、遂にトリガーを引いてもかちっ、かちっ、という間の抜けた音が聞こえるのみとなった。健の表情が初めて崩れる。
「ちっ……」
「終わりですか? じゃぁ、ここで死んでください——」
すっ、と。
祐介が、健の目の前に現れる。縮地、と呼ばれる、特殊な走行方法——剣術や剣道などの、近接戦闘武術の達人だけが身に着けることを許された、距離を圧縮する足遣い。長い努力と鍛錬を以て得ることができるはずのその技術を、彼は『偶然にも』全く努力することなく使えるのだ。
顔が近づく。この距離から逆転する手段。無いわけではない。健の異能である『Moon Light Fantasy』を利用すれば、遠くまで逃げることは可能だろう。幸いにして今は月が出ている。能力発動のトリガーはそろっていた。だが、そのためには一瞬の隙が必要だし、その間隙は、この状況で生み出すことは不可能に近い——
「……裏切者」
「……え?」
しかし。祐介は、健に向かって、ナイフや銃を突きつける、あるいはその肉体で打つ、と言ったことをしたわけではなかった。
「殺したいのはやまやまですよ。でも俺にも、知りたいことはある……貴方が……いいや、あんたがどうしてユミナ様を裏切ったのかだ。そして、どうしてあのヒトがあんたを赦しているのかだ。それを知るまで、あんたを殺すことはできない——教えろ」
「——それこそ、『好奇心は猫を殺す』、だぜ」
次の瞬間には、健は能力を発動させていた。空間が歪む。祐介が端正な顔を歪ませ、舌打ちをするのが聞こえる。
「じゃあね」
月に夢見る猫が映る——そんな錯覚の中。景色が、切り替わる。
探偵社の二階、健達のプライベートスペースへと。
「……好奇心は、猫を殺す、ねぇ」
健は苦笑して、鞄の中へと手を突っ込む。くしゃり、という感触。この事務所を出たときには、入っていなかったものだ。
「不用意なことは言うもんじゃないよ、祐介君」
その手には、一部の書類が携えられていた。『
健は先ほどの転移のときに、同時に祐介からこの書類を奪ってきていたのだ。これでマフィアたちが絵里を追う理由はほぼ確定した。あのスケッチブックに描いたモノを、現実のものとして顕現させる異能——あれと古代機を以て、何らかの現象を引き起こそうとしているに違いない。
だが、まだわからないことはある。何故絵里でなければならないのか。彼女がどうやらスケッチブック以外の場所に実体化する絵を描くことはできないらしい、ということは、注意深く観察すればすぐ分かる。そしてサイズは描いたモノと同寸——つまり、あまり大きなモノは創りだすことができないのだ。
そこから考えることができる、マフィアたちから見た絵里の『利用価値』は——
「健さん、どこに行ってたんだ」
「ん? ああ——ごめんごめん。集まってもらってたことを忘れてた」
思考が中断される。下手人は兵児だ。彼は無表情の中にも少しの不機嫌さをたたえながら、じっ、と健を見つめていた。
兵児だけではない。達也、絵里、かずのこの三人もまた、健のことを呆れたように見ている。
「それで。態々俺達を集めた理由は何なんだ?俺まで呼ぶなんて、何か重大なことなんだろ」
面倒くさがりの彼に相応しく、ほぼ全く表情を動かさずに、兵児は静かに問う。うんうん、と後ろでかずのこが頷くのが見える。「僕執筆したいんですけど」という顔だ。
これは変なことは言えないな……と、先ほどとはまたちょっと違った緊迫感を感じながら、健は笑った。持っていた書類を机の上に置き、皆の方を向く。
「うん、まぁ、大事なこと」
「勿体ぶらないで下さいよ。何なんです?」
達也が少しイラついた声で言う。これはまずい。彼を怒らせたらよくない。健は慌てて、
「単刀直入に言うと——絵里さんに、この探偵社に入ってもらおうと思ってね」
言った。ほう、へぇ、と言う声が上がる。
一番混乱しているのは、言われた本人——絵里の様だったが。
「え……えぇっ?」
「これはびっくりなのですー」
僕も驚き桃枝山椒枝、と妙なことを言いつつ、かずのこがお道化た。そしてそのままデスクチェアーにゆっくりと、謎の優雅な動作で座ると、特に何も入っていないグラスを口につけ、何かを飲むような動作をしてからこちらを見る。そして唐突に画風の違……キメた表情をとると、
「僕は大歓迎ですよ」
「それ言うためにその動作したの?」
「いやん、リッチ」
達也と兵児が反射的に突っ込みを入れる。ちなみに兵児は変わらず無表情、ついでに棒読みである。
「い、いや、そんなこと言ってる場合じゃなくて……っ!」
「じゃぁ決まりね」
「ちょ、ちょ―――ちょっと待ってください!」
わたわたと焦る絵里をよそに、健は笑顔で結論付ける。もちろん絵里は話題の終了を阻んだ。
「どうして急にそんなことを? それに、なんで私が……?」
眉根をよせて、不安そうに問う彼女。どうやらある種依頼者的立場でしかなかった自分が、唐突に『被依頼者』の側に入る、ということが不思議で仕方がないらしい。
健はんー、としばし考える。
「じゃぁさ、逆に聞くけど……絵里さんは、この先どうするつもりなの?」
「え……?」
「家に帰るのは無理なのは知ってるよね。それに今は僕たちが護衛してるけど、いつまでもこの状況が続くとは限らない。兵児君のおかげで前回、キョウヤの襲撃をはじき返すことができたけど、次もうまくいくとは限らない。兵児の『Smart Links』にも、召喚の限界はあるんだ。
逆に向こうには、まだ遭遇していない異能者がいるかもしれない。こちらの手札はほとんど見せているのに、向こうの全貌は把握できていないし。こないだそれで痛い目見てるでしょ」
絵里の脳裏に蘇るのは、小柄な黒髪の少年だ。狼のようなフードを被った彼は、人懐っこそうな笑顔と共に絵里に近づき、そして——
あの時のことを思い出すと、震えが走る。
「もちろん、護衛は続ける。けど、それにもいずれ限界がくる、ってことさ。こっちも仕事だ。お金はもらわないといけない。だけど、絵里さんにはそのお金にも限界がある——」
そうだ。
自分は、狙われているのだ。まっとうに働くことは赦されていない。護衛の人たちは、共に働くことはできまい。何より、同僚たちを危険にさらしてしまう——
ぞっ、と。
絵里の足元に、黒い穴が開いたような錯覚。虚無だ。無だ。何も見えない、底なしのヴォイド。このままなら、どこまででも引きずり込まれて——
「だからそのための考え、ってことですよ。そうでしょう、健さん」
達也のその一言で、はっ、と絵里は我に返る。彼を見れば、その真面目そうな顔をさらに真剣な表情で覆って、背の高い少年は言う。
「依頼者——ある種の『客』としてなら、報酬に限界が来た時点で俺たちは手を引かなくちゃいけない。たいして従業員——『仲間』としてなら、俺達にはそれを護るという義務がある。それは法律的にもそうだし、何より俺たちの信条がそうさせる。俺達よりもずっとずっと執念深くて、狡猾な異能マフィア達をしのぎ続けるためには、絵里さんに常に共に行動してもらわないといけない」
「なるほど、さすが達也。僕たちの頭脳。天才だね」
「いやいやまさかそこまで考えてなかったとか言いませんよね?」
「うん。言う」
「おかしい! 理不尽だ! 言い出しっぺがマトモに説得理由考えてないとか!!」
「……」
絵里は考える。
確かに、それは名案だ。それなら、自分の身を守りつつ、周りの人の心配もしなくていい。彼らが一人一人が予想もつかないほど強いことは知っている。自分が心配する必要がないほど。
だけど。
「でも、本当に私なんかが、いいんでしょうか。私がいる限り、みなさんに迷惑が——」
「そういうのはいいのいいの。仲間うちなら迷惑かけても当然よ」
「そうですよ~! ボクなんてプロになるまで何年兵児さんがカードゲームの世界大会で稼いできた大金をまるっと頂いてると思ってるんですか~!」
「ん……? おいちょっと待て。お前今妙な事——」
「えー、なんですか? すみません、耳にヒラメが入ってまして」
始まった茶番を呆然と見つめながら、絵里は内心で苦悶する。揺れ動く。迷惑をかけたくない。でも、この人たちになら、頼ってもいいのかもしれない、と。
その様子を、別の理由で逡巡しているのだと思ったのか、達也が後頭部をかきながら歯切れ悪く言う。
「まぁ、いきなりこんな胡散臭い探偵社に入れ、なんて言われても困りますよね」
「え……い、いえ。胡散臭いなんて、そんなことは──」
「まぁ胡散臭いのは仕方ないね。実際そうだし。だから、そうだなぁ……仮入社、もしくはアルバイトみたいな感じで。期限は、この事件が収拾するまで。どうかな?」
にこり、と。いつもの道化師のようなそれとは違う、柔らかい笑顔を浮かべて。
健が、右手を差し出す。
達也も。騒いでいたかずのこと兵児も。
「あ……」
知らず知らずのうちに、絵里の右手も、彼らの掌へと延びていた。
「よろしく、お願いします」
「うん、よろしくお願いされました」
「ようこそ、我らの探偵社へ」
「かずのこちゃんは絵里さんを歓迎しますよ~!」
「俺も面倒でないなら力になろう」
温かく自分を迎え入れてくれた彼らに、絵里の頬も緩む。ああ、これなら、きっと、大丈夫。
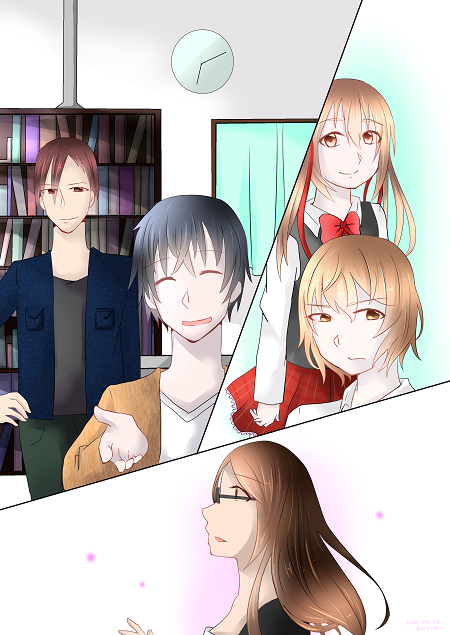
「じゃぁ、早速入社式と行こうか! たしか焼肉の機材をこないだ注文したはず——」
健が笑って、機材を探しに行こうと、一歩を踏み出した。
「そうですね。じゃぁ、ついでに退社式と行きましょうかぁ!」
「「「「──!?!?」」」」
その時だった。
歪む。空間が。それはある意味で健のそれと同じで、しかし根本的に違う能力。
健のそれは、空間を歪ませ『飛ぶ』技術。制約も多々ある代わりに、汎用性も高い。
たいして『それ』は、ただひたすら『繋げる』ことに特化した
異能名、『その扉の向こう側に』。
それを持っている人物は、一人だけ。
「みんな大好き、ろーがさんの登場だよ」
黒髪の少年が、立っていた。先ほどまでは誰もいなかったはずの、健達の背後。机の上——健が、祐介から奪い取った書類を置いていた、机の上だ。そこに、黒鉄狼牙が腰かけている。
にまにまと笑う彼の姿を見た瞬間、図られた——と、直感的に、健は悟った。同時に心の中で、何度も舌打ちをする。
祐介は、別に不用意に書類を持ち歩いていたわけではなかったのだ。健が彼の考えることをすべて把握できるのと同じように、彼もまた、健が考えることすべてを思いつく。
そして、決定的に二者を分けるのは——備わった、『幸運』だ。
祐介は、健の思い通りに動くことは無い。祐介の幸運が、健の思い通りに動かない未来、即ちは自分に有利な未来を引き寄せるからだ。
健は、祐介の思い通りに動く。なぜなら、祐介の幸運が、健が思い通りに動く未来を、つまりは自分に有利な未来を引き寄せるからだ。
完全に見透かされていたのだ。健が祐介から書類を奪うということは。
完全に予定されていたのだ。健が——すっかり、狼牙の能力の発動条件に関する考察を忘れているということは。
『その扉の向こう側に』は、「一度見た場所」をトリガーに、あらゆる場所と場所を繋げる力だ。だが、「場所」というのは、いったいどのような基準で選ばれているのか?
簡単だ——能力者の、主観である。
例えば。祐介が、書類をどこかの机の上に置いたとして。
その上に狼牙が立つとして。
——『書類の上という場所』を、『扉』を繋げる先の風景として、登録していたならば。
あの書類を健が奪い取り、そして机の上に置いた、という時点で、このプライベートルームは、彼の転移の範囲内……!
「やぁ……エース君」
背を伝う冷たい感触を必死で押さえつけながら、健は少年に呼びかける。彼はその名を聞いて露骨に顔をしかめた。
「その名で呼ぶな」
冷たい、氷のような。いや——獣が、冷酷に獲物を狙うような、目。それはその場にいる人間を。特に、戦いに慣れない絵里を凍り付かせるのには。十分だった。
「まぁいいです。そんなことより皆さんに残念なお知らせでーす!」
次の瞬間にはいつもの明るい笑顔に戻った狼牙は、直後、衝撃的な言葉を口にした。
「このビル、今、僕たちの方で完全に包囲させて貰ってまーす」
「……何っ……?」
窓の外を見る達也。彼の表情がこわばる。健にも分かる。なんというか、重圧。狼牙の言っていることは、真実だと、本能が告げている。
「達也、なんか解決方法ない?」
「無理です。完膚なきまでに囲まれてます」
珍しく、達也が即答でさじを投げる。
「なんだって、そいつはたいへんじゃぁないか!」
お道化て見せる健。
「はい、というわけで、健さんたちはおとなしく降伏しやがってくださいませませ~」
狼牙はにっこりと黒い笑みを浮かべる。ひっ、と、小さな悲鳴を上げる絵里。
「健さん……どうするつもりなんだ?」
兵児が問う。健はうーん、とうなると。
「うん、打つ手なし! 分かった、降伏しよう!」
両手を挙げて、たははー、と笑った。
「「「え?」」」
「え?」
探偵社の四人が驚いたように目をむき、健を見る。
そして誰より。
「……え?」
狼牙が、間抜けた声を上げた。
全て感想を見る:感想一覧
