| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
俺たちで文豪ストレイドッグスやってみた。
作者:絶炎with八咫烏
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動第2話「騒乱の序曲」
「――さてさて、どうしたものかな」
健がそう呟き、長めに伸びた黒髪の下に覗く顔にニコニコと笑みを浮かべる。女の氷柱のように鋭い視線を真っ向から受けても尚その様子を崩す事はなく、女が忌々しげに舌打ちした。その様子を見て健が苦笑し、それによって更に女が機嫌を損ねる。
女はその表情を一旦引っ込めるとその声音を冷静なものに戻して、静かに声を上げた。
「敢えて貴方のところに向かって見ましたが……失敗でしたね。江西達也は連れていないのですか?」
「それに関しては僕も驚いたよ……あと生憎と、彼は今出張中だ。ちょっと頼み事をしていてね」
「敵にそんな事バラしちゃっていいんですかー?あの人すっごく頭良さそうなんですけどー」
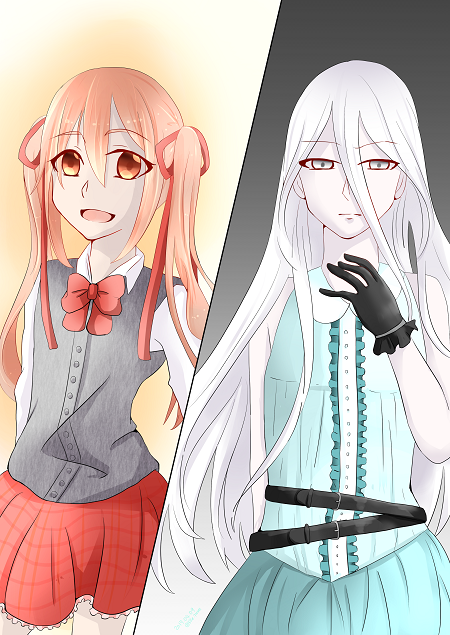
健の言葉を聞いた女――『カミサキ』は素早く周囲を視線のみで見回すと、それが本当だと確認したのか、ほんの少しだけ口端に笑みを浮かべる。その間に、健の後ろで待機していたツインテールの少女が不思議そうに健に問いを投げた。
「そういえば、お知り合いさんですかー?」
「うん?ああ、昔ちょっとね」
横目でウインクしつつぼかした健に少女が少しばかり訝しげな視線を向けるも、特に気にした様子も無く視線を戻す。気付けば先程の笑みも引っ込めた『カミサキ』は平静を取り戻し、あくまでも冷静な様子で手に持った銃を降ろした。
健の目が細まり、冷たい視線の応酬が行われる。
「……彼が居ないのなら、私にもまだ勝ち目はありますね。あの男と真正面からやったのでは、勝ち目がありませんから」
「へぇ、僕相手ならこの状況をどうにか出来るって?」
「無論、貴方の異能力は厄介ですが……逃げるくらいなら出来ます。あの化け物程ではない」
一歩、退く。即座に少女が反応して袖口から折り畳みナイフを抜き出し、『カミサキ』に向けて投擲する。ナイフは寸分違わず女に向かったが、女もまた手に持った銃で正確にナイフを撃ち落とす。高速移動する小さな的を撃ち落とす技術の高さもそうだが、この女の恐ろしさはその異能力の凶悪さだけに留まらないのだ。
退いた女の背後に、突然空間の歪みが出現する。その歪みから唐突に顔を出した少年が調子の良さそうな笑顔を浮かべて、『カミサキ』に声を掛けた。
「はいはい、呼ばれて飛び出てろーがさんですよ!貴女のピンチに即参上!」
「しまっ……!」
焦った様に健が走り出すも、到底間に合わない。直ぐに異能力を発動させようとするが、寸前で後ろの黒服達が一斉に射撃を再開する。銃弾が狙うのは健では無く、背後に控える二人。
即座に健がその『異能力』を発動させて銃弾を止めるも、その時既に『カミサキ』は歪みの中へと消えていた。
残った黒服達も、蜘蛛の子を散らす様に撤退していく。
彼らを捉えた所で、情報は得られないだろう。
「……くそ、面倒だ」
一つ舌打ちをして、健が肩を竦める。それを見た少女が「終わりですかねー」などと呟き、改めて女性に手を差し伸べた。
その手を取ってなんとか立ち上がると、顔にニコニコとした笑顔を戻した健が戻って来た。
「いやはや、無事で良かったよ、綾部さん」
「……!どうして、私の名前……」
「探偵ですから。取り敢えず、今の君が置かれている状況を説明したいんだけれど……」
健はそう切り出すと、突然思いついた様に「あ」と呟き、懐から携帯を取り出した。何かしら番号を打ち込み誰かに電話をかけると同時、それが繋がるまでの時間でぽつりと
「まあ、取り敢えずウチの事務所においで。やっすいお茶菓子でよければご馳走しよう」
そう、言ったのだった。
◇ ◇ ◇
「……それで、そいつが例の『絵描き』か?」
双樹がソファに座る絵里に鋭い視線を向け、その冷たい目を受けた彼女の体がビクリと震える。「まあまあ」と健が間に割って入り、双樹もまた興味無さげに目を逸らした。
健は自分もまた絵里の反対側のソファに座り、茶髪の少女もまた彼の横に座る。不意にパチンと健が両手を叩き、二人の視線を集めた。
「取り敢えず、まあ何が起こっているのか分からない節もあるだろう。君が一体どう言った事に巻き込まれて、どう言った状況に追い込まれたか――そこから話していこうか」
「……どういう事ですか」
「君だって、事がさっきので全て片付くとは思ってないんだろう?」
図星だった様で、彼女は俯いて黙り込む。あの路地裏で会った女、そして黒服の男達……あれは完全に、ドラマや小説なんかの世界で言う『裏側の住人』――マフィアやヤクザの類だ。
ああ言った人種は、まず一度狙いを定めた人間は逃さない。あの女……健が『カミサキ』と呼んだあの白髪の女は、絵里を殺すと言った。であれば、彼女は確実に絵里を殺そうとするだろう。まず確実に、絵里だけの力で逃げ切る事など不可能だ。
「そういう訳で、君には暫くの間、この事務所で寝泊まりしてもらう。ああ、着替えなんかは大丈夫、かずのこちゃんが用意してくれるから」
「僕!?」
「ウチの事務所に女の子は君しかいないんだ、当然でしょ?」
まるでコントでもするかのように言い合う二人を横目に、絵里は自身が持つスケッチブックに目を落とす。長年使っているはずなのに、未だその一ページたりとも埋まっていないそれは、長年彼女の絵を実体化させる触媒となり続けたものだ。
『舞えない黒蝶のバレリーナ』――綾部絵里が持つその異能は、スケッチブックに描いたモノを物質として実体化させる。しかし言ってしまえば、"ただそれだけ"の異能だ。わざわざ、そんな裏側の住人達がこの力を欲しがっているのか、検討もつかない。
「……暫くは危険だってことは、理解しました。それじゃあ、一旦帰って……」
「――何処に?」
「……へ?」
健が、不思議そうに首を傾げる。
次いで彼は、思いついたようにテレビの電源を付ける。そのチャンネルではニュースが報道されており、画面内のスタジオの画面には、見知った街が映されていた。
しかし画面の半分ほどは真っ黒な煙に覆われており、火事の報道なのだろうと理解する。
『マフィアによる放火!?一家全焼、二人分の焼死体。何の変哲もない一家に一体何が』
そんな見出しと共に、焼けたのであろう家に画面が切り替わる。未だその黒焦げの骨組みから煙を立ち上がらせるその家は、明らかに見覚えがある。
見覚えが、あるに決まっている。
「…………ぁ、……ぇ?」
何時も大学へ通う時、一度は見返す場所。
疲れた体を引きずって、その場所を見るたびに、帰ってきたのだと安らぎを覚えた場所。
「……う、そ……だ」
絵里が産まれてからずっと、20年近くをずっと暮らした場所。沢山の思い出、沢山の安心、それらが在った場所。
絵里を産み、そして育ててくれた両親と、笑顔を浮かべて笑いあった一軒家。
彼女の自宅が、焼け焦げた無残な姿となって、そこに写っていて――。
「ぁ、ああぁぁぁぁぁーーーーっ!?」
即座に、懐から携帯を取り出す。打ち慣れた番号を焦りながらも何とか間違えずに打ち込み、煩わしいコール音を上げてその相手へと繋げようとする。しかしいつまで経っても電話は掛からず、代わりに帰ってきたのは、無機質な電子音。
『お掛けになった電話番号は、現在使われておりません。番号をお確かめになって、もう一度――。』
切る。打ち間違えただけだ、そうに決まっている。少し焦っていた、それだけの話だ。焦るな、電波番号はしっかり覚えている、電話帳にも登録してある、正確に打ち込め。
今度こそ確かに、間違いの余地も何一つない程正確に、何度も確認して打ち込む。全て打ち終わってからコールし、携帯を耳に宛てた。しかし、やはり帰ってくるのは、不愉快な自動音声のみ。
嘘だ、こんなの。こんなこと。
『現場で見つかった焼死体はDNA鑑定により、この家の住人である綾部健三さん、綾部春香さんと見られており、現在、行方不明である夫妻の娘、綾部絵里さんを警察が捜索中との――』
「ーーっ!」
「ストップですよー」
直ぐに立ち上がった絵里の手を、『かずのこ』と呼ばれた少女が掴む。絵里が焦った様子でその手を振り払おうとするも、その前に少女が絵里の前に回り込んで、その頰を両手で挟み込んだ。
突然の事に困惑する絵里に、少女がにっこりと笑って話しかける。
「はーい、落ち着いてー。リラックスリラックス、深呼吸です。安心して下さいね、ご両親は無事ですからー」
「で、でも……っ、電話、繋がらなかったし……テレビでも……!」
「『そういう事にしている』だけです。素直に助かったって言っちゃうと、また狙われちゃいますからねー。たっちゃんが保護していますよ。安心して下さい」
「あ、たっちゃんっていうのは、この前僕と一緒に居た彼ね。ご両親はここから少し行った別の家に居るから、誰か後で護衛でも付けよう。なんなら、後で電話でもするといい、前の携帯は家と一緒に焼けてしまったから、新しい番号になるけどね」
そう言って健が手に持ったスマホを見せると、やや不安そうな顔をしながらもしっかりと生きている、自分の両親が写っていた。その傍らにはあの時の青年も写っており、写真下の文面には『任務完了』の旨が記されている。
安心したせいか、その場にへたり込んでしまう。一つ大きな溜息を吐いて、眼から零れ落ちそうになる涙をぐっと堪えた。少女が隣にかがみ、その背を優しく撫でる。
「ごめんごめん、少し意地悪だったかな」
「そうですよー、年頃の女の子はナイーブなんですからー」
少女が憤慨したように形だけ装って文句を言い、健が苦笑する。そんなやりとりをなんとか落ち着かせた心で眺め、冷静になっていくうちに一つの疑問が浮かんだ。
「そういえば……なんでそこまで、してくれるんですか?」
「うん?ああ、それは君の能力が……って言っても、これを言わなきゃ分かんないかな。一から説明するよ」
健は一つ指を立てて口を開く。
曰く、絵里の能力は絵に描いたものをなんだろうと具現化する――それは絵里自身も知っている力だ。だが、問題はそれによって具現化できる物にあるらしい。それを求めて、あのマフィア達はこの力を狙っているのだという。
「はーい、健さーん。それってなんでしょーかー!」
勢い良く手を上げながら言う『かずのこ』と呼ばれた少女に、健が笑って立てた指をピシリと向ける。
「いい質問だね、かずのこちゃん。それはね、『古代機 』と呼ばれるものだ。『能力を自在に生み出す機械』、と言えば分かりやすいかな。今はもう失われてるけどね……小腹空いたな、双樹くーん?」
「はいはい頼まれてたポテチね、そら、豚のように貪れ」
「痛い!」
気怠げに声を上げた健の顔面に双樹の投げたポテトチップスの袋がクリーンヒットし、大袈裟に仰け反りつつもそれをうけとめる。「ふつーに渡せないのー?」などと文句を垂れつつ、三人が囲むテーブルに袋を開いた。
「……とまあ、そんな訳で僕達探偵社は、君の護衛をする事になった。急で悪いけれど、まあ了承して欲しい」
「ちなみに悪いが、拒否権はない。アンタがあいつらに捕まると、相当に不味い事になるんでな。それ相応の不自由は覚悟してくれ」
双樹が後ろから顔を出し、そう補足する。それによって絵里の顔が暗く沈み、彼女は双樹に一つ問いを投げた。
「警察は、動いてないんですか?」
「動いてはいる、が、多分ダメだろう。警察は対異能者犯罪専門って訳じゃない、今もアジトに向かっちゃいるだろうが……まあ、返り討ちが妥当だな」
双樹が相変わらず無感情な瞳で、窓の外を見つめる。国家の守護者達を相手に散々な物言いだが、あの女――『カミサキ』を見てからだと、あながち間違いだとも言い切れなかった。
「……そうですか」
彼らが保護に動いてくれているとは言え、それほどの相手が自分を狙っていると言う事実。それが、酷く恐ろしかった。
◇ ◇ ◇
「……準備は良いな?突入するぞ、構えろ」
RATS ――警察に所属する特殊部隊、その隊長が、サブマシンガンを携えて右手を掲げる。それを合図に他の隊員達も各々の武器を構え、振り下ろすと共に扉を蹴破った。
次々と部屋の中に武装が施された隊員達が流れ込み、その銃口で部屋の中に存在する一切に照準を向ける。
「動くな、警察だ!武器を足下に置いて両手を上げろ!」
隊長がそう声を張り上げて、部屋の中心にいる五人にそう警告する。銃口を向けられたその五人――『カミサキ』と、彼女を守るように佇む四人の男が視線を彼に向け、しばし沈黙した後、ホルスターに入っていた拳銃を地面に置いた。
照準を一瞬たりとも彼女らから逸らさず、妙な動きを見せれば即刻射殺する。その許可は既に降りている。
「よし、武器は置いたな。なら、両手を頭の後ろに組んで――」
「お待ちしていましたよ、RATSの皆さん」
唐突に。
『カミサキ』が両手を広げて、歓迎の意を示すように演劇じみた動作を見せる。隊員達は警戒の姿勢を取って銃口を一斉に彼女へと集わせるが、彼女は何も臆した様子はない。
視線を集めきった事を把握した『カミサキ』は一つ頷くと、再度口を開いた。
「さて、まずは……両手を頭の後ろに組め、でしたか」
『カミサキ』はそう言って両手を上げ、そのまま頭の後ろに組む。妙に従順なその姿に困惑しつつも一つ頷いて、他の男達に視線を向ける。そうして同じように指示を出す――
寸前に。
『カミサキ』の手首が、何か光ったように見えた。
「――っ!?」
即座に銃器を構え直すが、飛来した極小の『何か』が特殊部隊専用の装備の隙間を抜け、素肌に突き刺さる。チクリとした感覚と共に全身に痺れが周り、隊長の体が崩れ落ちた。
「なーー」
「改めて、こんにちは。埼玉県警察RATS」
『カミサキ』がヘアピンに偽装した射出機を放り捨て、改めて大袈裟な素振りで挨拶をする。組んだ両手は下ろし、その両手に付けられていた手袋を外した。しなやかな細く、白い指が見え、ただそれだけで特殊部隊の隊員達に悪寒が走る。
ニィ、と口元を歪めた『カミサキ』は、ヒールの踵を鳴らして一歩を踏み出す。
「そして」
側に控える四人の男が、一斉に動き出す。咄嗟に隊員達が反応しようとするも、圧倒的に、絶望的に、遅過ぎた。
「さようなら」
――蹂躙が、始まる。
ページ上へ戻る健がそう呟き、長めに伸びた黒髪の下に覗く顔にニコニコと笑みを浮かべる。女の氷柱のように鋭い視線を真っ向から受けても尚その様子を崩す事はなく、女が忌々しげに舌打ちした。その様子を見て健が苦笑し、それによって更に女が機嫌を損ねる。
女はその表情を一旦引っ込めるとその声音を冷静なものに戻して、静かに声を上げた。
「敢えて貴方のところに向かって見ましたが……失敗でしたね。江西達也は連れていないのですか?」
「それに関しては僕も驚いたよ……あと生憎と、彼は今出張中だ。ちょっと頼み事をしていてね」
「敵にそんな事バラしちゃっていいんですかー?あの人すっごく頭良さそうなんですけどー」
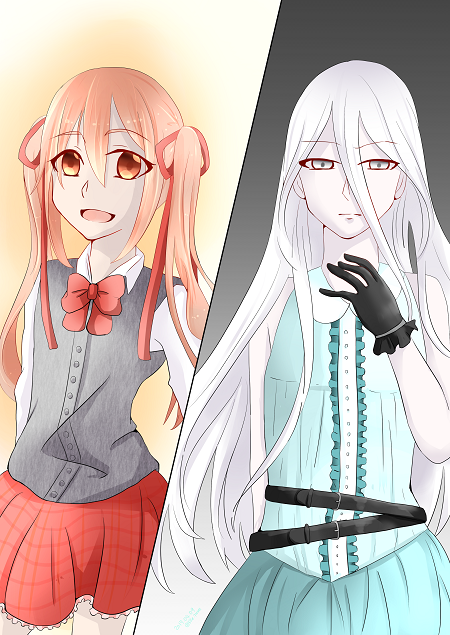
健の言葉を聞いた女――『カミサキ』は素早く周囲を視線のみで見回すと、それが本当だと確認したのか、ほんの少しだけ口端に笑みを浮かべる。その間に、健の後ろで待機していたツインテールの少女が不思議そうに健に問いを投げた。
「そういえば、お知り合いさんですかー?」
「うん?ああ、昔ちょっとね」
横目でウインクしつつぼかした健に少女が少しばかり訝しげな視線を向けるも、特に気にした様子も無く視線を戻す。気付けば先程の笑みも引っ込めた『カミサキ』は平静を取り戻し、あくまでも冷静な様子で手に持った銃を降ろした。
健の目が細まり、冷たい視線の応酬が行われる。
「……彼が居ないのなら、私にもまだ勝ち目はありますね。あの男と真正面からやったのでは、勝ち目がありませんから」
「へぇ、僕相手ならこの状況をどうにか出来るって?」
「無論、貴方の異能力は厄介ですが……逃げるくらいなら出来ます。あの化け物程ではない」
一歩、退く。即座に少女が反応して袖口から折り畳みナイフを抜き出し、『カミサキ』に向けて投擲する。ナイフは寸分違わず女に向かったが、女もまた手に持った銃で正確にナイフを撃ち落とす。高速移動する小さな的を撃ち落とす技術の高さもそうだが、この女の恐ろしさはその異能力の凶悪さだけに留まらないのだ。
退いた女の背後に、突然空間の歪みが出現する。その歪みから唐突に顔を出した少年が調子の良さそうな笑顔を浮かべて、『カミサキ』に声を掛けた。
「はいはい、呼ばれて飛び出てろーがさんですよ!貴女のピンチに即参上!」
「しまっ……!」
焦った様に健が走り出すも、到底間に合わない。直ぐに異能力を発動させようとするが、寸前で後ろの黒服達が一斉に射撃を再開する。銃弾が狙うのは健では無く、背後に控える二人。
即座に健がその『異能力』を発動させて銃弾を止めるも、その時既に『カミサキ』は歪みの中へと消えていた。
残った黒服達も、蜘蛛の子を散らす様に撤退していく。
彼らを捉えた所で、情報は得られないだろう。
「……くそ、面倒だ」
一つ舌打ちをして、健が肩を竦める。それを見た少女が「終わりですかねー」などと呟き、改めて女性に手を差し伸べた。
その手を取ってなんとか立ち上がると、顔にニコニコとした笑顔を戻した健が戻って来た。
「いやはや、無事で良かったよ、綾部さん」
「……!どうして、私の名前……」
「探偵ですから。取り敢えず、今の君が置かれている状況を説明したいんだけれど……」
健はそう切り出すと、突然思いついた様に「あ」と呟き、懐から携帯を取り出した。何かしら番号を打ち込み誰かに電話をかけると同時、それが繋がるまでの時間でぽつりと
「まあ、取り敢えずウチの事務所においで。やっすいお茶菓子でよければご馳走しよう」
そう、言ったのだった。
◇ ◇ ◇
「……それで、そいつが例の『絵描き』か?」
双樹がソファに座る絵里に鋭い視線を向け、その冷たい目を受けた彼女の体がビクリと震える。「まあまあ」と健が間に割って入り、双樹もまた興味無さげに目を逸らした。
健は自分もまた絵里の反対側のソファに座り、茶髪の少女もまた彼の横に座る。不意にパチンと健が両手を叩き、二人の視線を集めた。
「取り敢えず、まあ何が起こっているのか分からない節もあるだろう。君が一体どう言った事に巻き込まれて、どう言った状況に追い込まれたか――そこから話していこうか」
「……どういう事ですか」
「君だって、事がさっきので全て片付くとは思ってないんだろう?」
図星だった様で、彼女は俯いて黙り込む。あの路地裏で会った女、そして黒服の男達……あれは完全に、ドラマや小説なんかの世界で言う『裏側の住人』――マフィアやヤクザの類だ。
ああ言った人種は、まず一度狙いを定めた人間は逃さない。あの女……健が『カミサキ』と呼んだあの白髪の女は、絵里を殺すと言った。であれば、彼女は確実に絵里を殺そうとするだろう。まず確実に、絵里だけの力で逃げ切る事など不可能だ。
「そういう訳で、君には暫くの間、この事務所で寝泊まりしてもらう。ああ、着替えなんかは大丈夫、かずのこちゃんが用意してくれるから」
「僕!?」
「ウチの事務所に女の子は君しかいないんだ、当然でしょ?」
まるでコントでもするかのように言い合う二人を横目に、絵里は自身が持つスケッチブックに目を落とす。長年使っているはずなのに、未だその一ページたりとも埋まっていないそれは、長年彼女の絵を実体化させる触媒となり続けたものだ。
『舞えない黒蝶のバレリーナ』――綾部絵里が持つその異能は、スケッチブックに描いたモノを物質として実体化させる。しかし言ってしまえば、"ただそれだけ"の異能だ。わざわざ、そんな裏側の住人達がこの力を欲しがっているのか、検討もつかない。
「……暫くは危険だってことは、理解しました。それじゃあ、一旦帰って……」
「――何処に?」
「……へ?」
健が、不思議そうに首を傾げる。
次いで彼は、思いついたようにテレビの電源を付ける。そのチャンネルではニュースが報道されており、画面内のスタジオの画面には、見知った街が映されていた。
しかし画面の半分ほどは真っ黒な煙に覆われており、火事の報道なのだろうと理解する。
『マフィアによる放火!?一家全焼、二人分の焼死体。何の変哲もない一家に一体何が』
そんな見出しと共に、焼けたのであろう家に画面が切り替わる。未だその黒焦げの骨組みから煙を立ち上がらせるその家は、明らかに見覚えがある。
見覚えが、あるに決まっている。
「…………ぁ、……ぇ?」
何時も大学へ通う時、一度は見返す場所。
疲れた体を引きずって、その場所を見るたびに、帰ってきたのだと安らぎを覚えた場所。
「……う、そ……だ」
絵里が産まれてからずっと、20年近くをずっと暮らした場所。沢山の思い出、沢山の安心、それらが在った場所。
絵里を産み、そして育ててくれた両親と、笑顔を浮かべて笑いあった一軒家。
彼女の自宅が、焼け焦げた無残な姿となって、そこに写っていて――。
「ぁ、ああぁぁぁぁぁーーーーっ!?」
即座に、懐から携帯を取り出す。打ち慣れた番号を焦りながらも何とか間違えずに打ち込み、煩わしいコール音を上げてその相手へと繋げようとする。しかしいつまで経っても電話は掛からず、代わりに帰ってきたのは、無機質な電子音。
『お掛けになった電話番号は、現在使われておりません。番号をお確かめになって、もう一度――。』
切る。打ち間違えただけだ、そうに決まっている。少し焦っていた、それだけの話だ。焦るな、電波番号はしっかり覚えている、電話帳にも登録してある、正確に打ち込め。
今度こそ確かに、間違いの余地も何一つない程正確に、何度も確認して打ち込む。全て打ち終わってからコールし、携帯を耳に宛てた。しかし、やはり帰ってくるのは、不愉快な自動音声のみ。
嘘だ、こんなの。こんなこと。
『現場で見つかった焼死体はDNA鑑定により、この家の住人である綾部健三さん、綾部春香さんと見られており、現在、行方不明である夫妻の娘、綾部絵里さんを警察が捜索中との――』
「ーーっ!」
「ストップですよー」
直ぐに立ち上がった絵里の手を、『かずのこ』と呼ばれた少女が掴む。絵里が焦った様子でその手を振り払おうとするも、その前に少女が絵里の前に回り込んで、その頰を両手で挟み込んだ。
突然の事に困惑する絵里に、少女がにっこりと笑って話しかける。
「はーい、落ち着いてー。リラックスリラックス、深呼吸です。安心して下さいね、ご両親は無事ですからー」
「で、でも……っ、電話、繋がらなかったし……テレビでも……!」
「『そういう事にしている』だけです。素直に助かったって言っちゃうと、また狙われちゃいますからねー。たっちゃんが保護していますよ。安心して下さい」
「あ、たっちゃんっていうのは、この前僕と一緒に居た彼ね。ご両親はここから少し行った別の家に居るから、誰か後で護衛でも付けよう。なんなら、後で電話でもするといい、前の携帯は家と一緒に焼けてしまったから、新しい番号になるけどね」
そう言って健が手に持ったスマホを見せると、やや不安そうな顔をしながらもしっかりと生きている、自分の両親が写っていた。その傍らにはあの時の青年も写っており、写真下の文面には『任務完了』の旨が記されている。
安心したせいか、その場にへたり込んでしまう。一つ大きな溜息を吐いて、眼から零れ落ちそうになる涙をぐっと堪えた。少女が隣にかがみ、その背を優しく撫でる。
「ごめんごめん、少し意地悪だったかな」
「そうですよー、年頃の女の子はナイーブなんですからー」
少女が憤慨したように形だけ装って文句を言い、健が苦笑する。そんなやりとりをなんとか落ち着かせた心で眺め、冷静になっていくうちに一つの疑問が浮かんだ。
「そういえば……なんでそこまで、してくれるんですか?」
「うん?ああ、それは君の能力が……って言っても、これを言わなきゃ分かんないかな。一から説明するよ」
健は一つ指を立てて口を開く。
曰く、絵里の能力は絵に描いたものをなんだろうと具現化する――それは絵里自身も知っている力だ。だが、問題はそれによって具現化できる物にあるらしい。それを求めて、あのマフィア達はこの力を狙っているのだという。
「はーい、健さーん。それってなんでしょーかー!」
勢い良く手を上げながら言う『かずのこ』と呼ばれた少女に、健が笑って立てた指をピシリと向ける。
「いい質問だね、かずのこちゃん。それはね、『
「はいはい頼まれてたポテチね、そら、豚のように貪れ」
「痛い!」
気怠げに声を上げた健の顔面に双樹の投げたポテトチップスの袋がクリーンヒットし、大袈裟に仰け反りつつもそれをうけとめる。「ふつーに渡せないのー?」などと文句を垂れつつ、三人が囲むテーブルに袋を開いた。
「……とまあ、そんな訳で僕達探偵社は、君の護衛をする事になった。急で悪いけれど、まあ了承して欲しい」
「ちなみに悪いが、拒否権はない。アンタがあいつらに捕まると、相当に不味い事になるんでな。それ相応の不自由は覚悟してくれ」
双樹が後ろから顔を出し、そう補足する。それによって絵里の顔が暗く沈み、彼女は双樹に一つ問いを投げた。
「警察は、動いてないんですか?」
「動いてはいる、が、多分ダメだろう。警察は対異能者犯罪専門って訳じゃない、今もアジトに向かっちゃいるだろうが……まあ、返り討ちが妥当だな」
双樹が相変わらず無感情な瞳で、窓の外を見つめる。国家の守護者達を相手に散々な物言いだが、あの女――『カミサキ』を見てからだと、あながち間違いだとも言い切れなかった。
「……そうですか」
彼らが保護に動いてくれているとは言え、それほどの相手が自分を狙っていると言う事実。それが、酷く恐ろしかった。
◇ ◇ ◇
「……準備は良いな?突入するぞ、構えろ」
次々と部屋の中に武装が施された隊員達が流れ込み、その銃口で部屋の中に存在する一切に照準を向ける。
「動くな、警察だ!武器を足下に置いて両手を上げろ!」
隊長がそう声を張り上げて、部屋の中心にいる五人にそう警告する。銃口を向けられたその五人――『カミサキ』と、彼女を守るように佇む四人の男が視線を彼に向け、しばし沈黙した後、ホルスターに入っていた拳銃を地面に置いた。
照準を一瞬たりとも彼女らから逸らさず、妙な動きを見せれば即刻射殺する。その許可は既に降りている。
「よし、武器は置いたな。なら、両手を頭の後ろに組んで――」
「お待ちしていましたよ、RATSの皆さん」
唐突に。
『カミサキ』が両手を広げて、歓迎の意を示すように演劇じみた動作を見せる。隊員達は警戒の姿勢を取って銃口を一斉に彼女へと集わせるが、彼女は何も臆した様子はない。
視線を集めきった事を把握した『カミサキ』は一つ頷くと、再度口を開いた。
「さて、まずは……両手を頭の後ろに組め、でしたか」
『カミサキ』はそう言って両手を上げ、そのまま頭の後ろに組む。妙に従順なその姿に困惑しつつも一つ頷いて、他の男達に視線を向ける。そうして同じように指示を出す――
寸前に。
『カミサキ』の手首が、何か光ったように見えた。
「――っ!?」
即座に銃器を構え直すが、飛来した極小の『何か』が特殊部隊専用の装備の隙間を抜け、素肌に突き刺さる。チクリとした感覚と共に全身に痺れが周り、隊長の体が崩れ落ちた。
「なーー」
「改めて、こんにちは。埼玉県警察RATS」
『カミサキ』がヘアピンに偽装した射出機を放り捨て、改めて大袈裟な素振りで挨拶をする。組んだ両手は下ろし、その両手に付けられていた手袋を外した。しなやかな細く、白い指が見え、ただそれだけで特殊部隊の隊員達に悪寒が走る。
ニィ、と口元を歪めた『カミサキ』は、ヒールの踵を鳴らして一歩を踏み出す。
「そして」
側に控える四人の男が、一斉に動き出す。咄嗟に隊員達が反応しようとするも、圧倒的に、絶望的に、遅過ぎた。
「さようなら」
――蹂躙が、始まる。
全て感想を見る:感想一覧
