| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
ソードアート・オンライン 舞えない黒蝶のバレリーナ (現在修正中)
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。 ページ下へ移動第一部 ―愚者よ、後ろを振り返ってはならない
第1章
第2話 歓喜する魂
前書き
医学の知識はありませんので、もしかしたらありえないことを書いているかもしれませんが、そこはスルーして頂けると嬉しいです……。
【追記】
2015.08.19
修正済
追加イラスト2枚有
【追記】
2015.08.19
修正済
追加イラスト2枚有
――――――――2022年11月。
最近のテレビは、もうすぐ発売のゲーム―――――≪ソードアート・オンライン≫の話題で持ち切りだ。
……まあいつもの私なら、ゲームなんて無視するだろう。興味なし、と。
けれど、4年前のあの日、私は変わった。……否、変わらざるを得なかった。
――――左足の自由と、右下肢。
それがあの事故で失ったもの。
ただ、右足は神経信号こそは守られたため、今は金属製の義足を装着している。左足に関しては麻痺が残り、動かすことも出来ない。
……これは、バレリーナとしての死を意味する。
今の私には、バレエでのポジションの1番――――両足のかかとの裏どうしをつけ、足の付け根から左右に開いて立つ立ち方――――さえ出来ないのだから。基本中の基本あり、バレエをやっていない人でも出来ることなのにも関わらず。
それでももしかしたら、手の振りだけでも何か表現出来るのではないかと、最初は色々と試していた。
けれど、何かが違う。私がやりたいのは、もっと、もっと全身を使う美しいバレエ。
左足に関してはリハビリ次第で日常生活で支障が無いくらいには回復するだろうと、医者には言われた。だが、それでは意味が無いのだ。
……左足が動かせるようになっても、義足を装着したとしても、あの頃には戻れない。
あの頃のようには踊れない。
ならば、私が存在を許されている場所はどこなのだろう。
“天才少女”であることを望んでいた周囲の者は離れていく。煩わしいくらいに張り付いてきた学校や教室の生徒は影で噂話をしたり、見下すようになった。両親は一見変わっていないように見えても、ふとした瞬間に腫物を扱うように接する。……“天才少女”にポジションを奪われていた人たちは同情するように泣いていたが、その裏では一体どんな声で笑っているのだろう。
……私は悟った。
もう、あの日のように舞うことは出来ない……、つまり、私には何も残っていないと。価値など無いんだと。
バレリーナとしても死んだけれども、あの日、“桐ケ谷紅葉”も死んだのだ、と。
その事実は、あの事故の前と後の周囲の温度差を比べたら火を見るよりも明らかだった。
だから、足掻くことをやめてしまった。……いや、正確に言えば、やる気力すら湧かなかったと言う方が正しいかもしれない。
……それはバレエだけではなく、絵も、演劇も、弓道も。かつての“紅葉”が好きだったものすべてのことに対して、以前のような高揚感が無くなっていた。
頑張るだけ、願うだけ“無駄”だと思ってしまったから。
そして一度気づいてしまうと、延々と意味の無い時間が続く希薄な毎日になった。
何をしても、どこにいても。
いつも『こうじゃない、何かが違う』と誰かが泣き叫んでいた。
鬱陶しいくらいに、いつも、いつも。……その正体はよく視えないけれど。
ふっと、幼い頃によく聴いた童謡が頭をよぎる。まるで池に落ちたドングリみたいだ。山に帰りたいと泣いて、戻れるはずのない場所を望んだドングリみたいだ。
「……はあ」
私は大きなため息をついた。深く、長く、細く。
――――あれから4年の月日が流れた。
残酷で、空虚な、宙に漂うような日々が続いて、こんな所まで来ていた。
ただまあ、車椅子で過ごさなければいけない生活になったとはいえ、部屋に引きこもったりはしなかった。というのも、事故後はスグに無理やり連れ出されるようになったのだ。
『色とりどりの景色を見て、空気を吸って、今しか出来ない経験をしようよ! ずっと家に居たらさ、腐っちゃうよ。あたしがモミの足の代わりになるから!!』
そう言って、スグは私の車椅子を押した。当時小学4年生になったばかりの彼女にそれは重かっただろうに、両親の反対を押し切って、一歩一歩、ゆっくりと街の中を進んだ。
事故が起きた日は身が凍るんじゃないかと危惧するほど寒かったというのに、もう外は青々とした葉が木々を彩っていた。
「きっと、もうすぐ梅雨になるね~。嫌だなぁ」
「……そう、だね」
「もう、もっと楽しもうよ~! ……あ、ねえねえ、ゴールデンウィークはどこに行く?」
「…………」
私は俯いて、自分の手先を見る。自然と両の太ももが視界に入ってきた。右足の質量はスカートの上から全く感じられなくて、見る度に現実を突きつけられる。
思わず視界を外したけれど、今度は目の居場所がなくなった。
しかし、まるで私の思考までも読み取ったかのようなタイミングで、
「モミ、見てみて! 綺麗な花がいっぱい咲いてるよー!!」
スグの弾けるような声に釣られて顔を上げた。目の前に白い花が飛び込んでくる。
「あの花、名前はなんだろうね」
「クチナシ」
疑問を口にするスグに、間髪入れずに答える。すると彼女はコテンと首を傾げ、
「……クチナシ?」
「そう。……あと、さっき通った庭にカーネーションが咲いていたよ。ザクロの木とか、ゼラニウムの鉢もあったかな」
「へえ~」
スグが嬉しそうにニコニコと笑いながら、感嘆の声を上げる。両手を合わせる彼女の表情はイルミネーションの光のように輝いていた。何がスグをそうさせているんだろう。
「やっぱりモミは物知りだな~」
「そんなことないよ。ちょっと記憶力が良いだけ」
「ええー、そう? ……じゃあ、家に帰ったら漢字の練習しようよ。来週小テストがあってさー」
「……ちょっと、それ私が小テスト解けって言うの」
「正解!」
「正解じゃないよ、もう!」
「あははっ」
明るく大きな笑い声に、私も思わず吹き出す。途端に、彼女がこれ以上にないほど顔を綻ばせた。私は目を細めて、
「……スグ」
「何?」
「ありがとね」
一瞬、不意を突かれた時のような間の抜けた顔になった。でも、すぐに歯を見せて笑う。
「こんなのお安い御用だよ!」
キラキラと輝く眩しい笑顔。何も変わらない澄んだ表情。
落下していくだけだった“私”の体に、いつの間にか一本の糸が巻き付いていた。
――――それからは、スグと一緒によく外出をするようになった。もしかしたら、事故の前よりも頻繁に出掛けるようになったかもしれない。
本当に、色々な場所へ連れ回された。動物園や水族館等の定番スポットはもちろんのこと、博覧会やプラネタリウム、ミュージカルからクラシックコンサートまで。果てには絶景を望むことが出来るハイキングコースや公園、何百種類もの花が咲き誇る美しい花園にも連れて行ってもらった。
『色とりどりの景色を見て』と言った彼女は、本当にその言葉通りにしてくれたのだ。
一体どこでそんな場所を見つけてきたんだと、首を傾げてしまうほどの情報量だった。しかも私の体の事を考慮してか、完璧にコースを作り上げて。……自分の時間を切り裂いて、私のために。元々パソコン関係は苦手で、学校の授業以外で触ったことなんてなかったはずなのに、必死にローマ字表と格闘して覚えてしまうまでキーボード入力をしていたことを私は知っている。
……ただ、スグには申し訳ないけれど、以前のように楽しいと純粋に心が躍ることは無くなった。どこへ行っても、どんなに美しいはずの景色を見ても、胸に穴が開いているみたいに感情がすり抜けていく。
それはスグも分かっているようで、必死に私を楽しませようとフォローしてくれた。諦めずに、何度も、何度も私を外の世界へ引っ張ってくれた。
――――そのおかげもあってか、気付いた時には車椅子での移動にはずいぶん慣れていたのだ。一人で十分行動出来るくらいに。
ちなみに、短時間の移動ならばロフストランドクラッチ――――前腕部支持型杖とも呼ばれるもので、前腕を通すカフとグリップで体重を支えるもの――――を右手で使用している。だが、外へ行くにはやはり車椅子を使わなければいけない。杖の支えがあるとはいえ右足で全体重を支えなければいけないので、義足の接続部への負担が大きい。よって、長時間の移動をすることには向いておらず、せいぜい家の中だけだ。
しかし、私をこんな風に行動出来るようにしてくれたのは他でもないスグだろう。
彼女には感謝してもしきれない。
「モミ~、入ってもいい?」
するとそのスグが、声を伸ばしながら軽くドアをノックしてきた。私は浮かべていた笑みを慌てて消し去り、膝の上に乗せていた小ぶりのバッグを机の上へ置く。
「いいわよ」
「はーい」
声と共にドアが開き、中学校の制服を身に付けたスグが顔をのぞかせた。今日は土曜日だが、おそらくいつものように部活へ行くのだろう。
「スグ、どうしたの?」
「ほらっ、今日も出掛けるんでしょ? 途中まで一緒に行かない?」
「いいけれど……、私、もう少し時間が掛かるわよ」
「大丈夫、大丈夫! あたしも手伝うし!」
そう言うが早いか、手慣れた調子で私の外出の準備を始める。こうなってしまったら、もうスグは止められないだろう。素直に手伝ってもらった方が早く終わる。私は苦笑いを作り、肩をすくめた。
「今日もあそこに行くんでしょ?」
「ええ、そうだけれど……、今日はその前に人と会う約束をしていて……」
「人と会う約束?」
スグがバッと私の方を振り返った。目を丸くさせ、驚いたような表情で私の顔を凝視してくる。けれどすぐに、
「……ああ、なるほど。幸歌さんか」
私が補足を入れる隙もなく一人で解決させ、ポンと手を打った。
「そう、幸歌よ」
「会うのは1年ぶりくらいじゃない?」
「そうね……、去年は私も幸歌もバタバタしていたし、4月に入ってからも忙しかったから」
ハンカチとポケットティッシュをバッグに入れながら口にした。
――――今でも思い出せる。
幸歌が事故を聞きつけて病室に駆け込んできたとき、泣きそうな顔をしながらも言ってくれた言葉を。
それは頭にしっかりと焼き付いていて、離れない。
『大丈夫だよ。私がいるから』
頭を優しく撫でながら、私の傍にいてくれた。
私の瞳を、まるで逃すまいとでも言うように、ずっと見ていてくれたのだ。
そんな幸歌は、告げていた通り私の事故の翌年――――学年が変わる頃に引っ越して行った。けれどそれまでは、ほとんど日をおかずにお見舞いに来てくれたのだ。看護師さんに私の家族だと勘違いされてしまうくらいに。
詳しいことは知らないが、幸歌は直前まで引っ越すことを渋ったらしい。私の傍を離れたくないと泣いて、彼女のお姉さんを困らせたそうだ。
結局、幸歌のお姉さんとスグが連絡を取り合い、私と幸歌が文通出来るようにするということで落ち着いた。
それからは、お互い携帯電話を持ちメールが出来るようになっても、少しくらい忙しくても、途絶えさせずに文通が続いている。幸歌からの手紙はそれだけで束を作れるようになり、物がほとんど無い殺風景な私の部屋で、確かな色を放っていた。
「幸歌さんっていい人だよね」
「ええ、そうね」
いつも文頭で、『困っていることはないか、体調を崩していないか』と聞いてくる。優しくて心配性な、掛け替えのない大切な親友だ。
「……まったくモミったら、本当に幸歌さんが好きなんだね」
「もちろんよ。幸歌は私の大事な友人だもの」
「はいはい。……もう、そこまでハッキリ言われると複雑だわ……」
「……は?」
「なんでもありませーん」
ひょいと肩を上げるスグを私は不思議に思いながら、部屋の壁に取り付けられた時計を見上げた。思っていたよりも時間が過ぎていて、慌ててスグの手を止めさせる。
「もう大丈夫よ。これ以上時間を取らせるのは悪いわ。今日も部活があるのでしょう?」
「そんな……、平気だよ」
「駄目よ。時間は守らなくてはいけないわ」
不服そうに唇を尖らせるスグの背中を、手を伸ばしてポンッと軽く叩く。私の動きが制限されていることをスグは十分理解しているから、強く理由を主張して背中を叩けばそれ以上粘ることはしない。
スグは荷物を肩に掛けると、ゆっくりとした足取りで扉に近づいて行った。しかしドアノブに手を乗せたところで私の方へ振り返り、
「ねえモミ、今度友達が入っている吹奏楽部が大会に出るんだけど、日曜日だし3人で応援に行かない?」
「……3人?」
「そう! あたしと、モミと、お兄ちゃんで!」
「――――スグ」
先ほどまでと口調は変わっていない。しかしその声の裏には、どこか願うような力強さがあった。ちょうど七夕に短冊へ願い事を書くみたいに。
私は無意識に目をそらす。
「…………悪いけれど」
「モミ……」
ガッカリしたように、悲しそうに、スグの声音が微かに震える。
「……こ、今回は断らせないんだからね!」
「…………スグ」
「……何でよ、どうして。あたしたち、あんなに仲良かったじゃない!」
「スグ!」
「モミだって、あの日3人で交わした“約束”を覚えてるでしょ!?」
「…………」
スグの必死な表情を見ていられなくて、顔をそらした。唇を噛み締める。
――――覚えてる。
私は、私とスグは覚えている。……けれどそれは、“あの人”も同じように覚えている確証には決してならない。
そもそも、仮に“彼”も覚えていたとしても、あの“約束”がすでに崩れ去っているのは現然たるものだった。
「……色々な理由を付けて3人で行きたがらないよね。小さい頃みたいに、お兄ちゃんとふざけ合うこともないし」
スグは知らない。
――――スグだけが、私たち“兄妹”の真実を知らないのだ。
私は、なんて残酷なことをスグにしているのだろう。あと数年経てば両親から知らされるからと、先延ばしして、隠し通している。
……きっと、怖いのだ。畏怖しているのだ。他でもない、“アイツ”が邪魔をするのだ。いつも、いつも、枯れて潰れた声で叫び続けて、私を不快にさせる “アイツ”が。
「……そんな、もうふざけ合うような歳でもないでしょう?」
「そうだけど……、そうだけど、あたしは……っ」
「スグ。私たちはもう、無邪気な子どもではないのよ。……少なくとも私は、ただ純粋に日々を過ごしていた頃には戻れないわ」
膝の上に乗せていた両手を握りしめた。ロングスカートに皺を作る。
翅を失えば、どんなに美しかった蝶であっても、生気を完全に喪失した醜い死骸に過ぎないのだ。
「……悲しいな。モミがあたしを置いて、先へ行ってしまったみたい」
「私はもう戻れないわ。ならば、先へ進むしかないのよ」
たとえそれが、体の肉を少しずつ切り刻まれていくような激痛に、この命を終えるまで苦しめられる道であったとしても。美しい過去に縋り付くことは、私には許されていないのだ。
愚かな罪人は、てらてらと光る猛毒が塗られた裁縫針の上を、素足で歩むしかない。数えることなど不可能であると言い切っても良いくらい針の先が迎え撃っていたとしても。立ち止まることも、駆け抜けることも、助けを求めることも出来ない。ただただ無慈悲で、冷酷で、孤独なのだ。
「けれどね、スグ。あなたまで急ぐことはないわ」
苦しみもがくのは、歯がガチガチと音を立てるくらい寒い。光を望むなんて滑稽に思えるほどの、果てしなく広がる暗黒の洞窟が続く。歩いても、歩いても、……歩き疲れて息が絶え絶えになっても、出口はおろか行き止まりさえ見つからない。いつ終わるのか、それすら分からない。自分がどこへ向かっているのかも分からない。
そもそもどうしてこの場所に居るのか、その理由を見失いそうになるのだ。
「……モミ、それってどういう……?」
「分からなくて良いわ。けれど、これだけは覚えていてちょうだい」
眉間に皺を寄せて、口をぎゅっと引き締めるスグへゆっくり近づいていく。腕を伸ばして、彼女の肩に手を置いた。
……あなたには、太陽の光がさんさんと降り注ぐ場所で生きて行ってほしい。
そう願うことだけが、私に出来る最善のことだった。
「――――来なくても良い場所だってあるのよ」
スグの表情が一層険しいものへと変わっていく。
「来なくても……、良い場所?」
「考えなくてもいいわ。ただ、覚えているだけでいいのよ」
「何それ。意味が分からないよ」
「……自分が幸せになれると思った道を、ちゃんと選び取るだけで良いの」
いつか、私が取り返しのつかないことになったとしても。スグまで追いかけて来なくても良いのだ。
スグは優しい。……けれど、それだけ危うさもあるのだ。
「……や、やだ。何なの、まるで遺言みたいじゃない!」
肩に置いていた手が、バッと振り払われた。すぐさま視線を戻すと、スグがわなわなと体を震わせ、ギッと目尻を吊り上げている。
「それに、その“来なくても良い場所”にモミがいるってことじゃないの!?」
顔を真っ赤にして激昂する彼女を、“私”は静かに見つめる。何も言わず、視線も動かさず、表情も変えず。するとそんな私に痺れを切らしたのか、スグが飛び掛かかってくるような勢いで私の両肩を掴んだ。力加減が出来ないほど感情が高ぶっているのか、爪が肉に食い込む。
しかし、“私”はそれでも、何の感情も動かさない。スグの整った顔が歪んだ。
「何がモミを苦しめているの!? 何がそうさせているの!? ……やっぱりあたし、分かんないよっ! ちゃんと教えてよ!!」
ハラリと舞った雫が、私の頬を濡らした。苦痛に満ちた、絞り出すような声が落ちてくる。
「3人で笑っていたあの頃に、戻りたいよ……っ!!」
肩を掴む両手が、フルフルと細かく震えていた。私は短くため息を吐き出すと、そっとその手を降ろさせる。
「――――スグ」
俯き加減だったショートヘアの少女が、ビクリと体を跳ねさせた。恐る恐るといった風に、顔が上げられる。
「スグ」
赤くさせた両目が、私の両目とぶつかった。瞬間、悔しそうな、何かを察して諦めたような、それでいて縋るような――――、そんな感情が複雑に入り混じった面持ちになる。
私は息を吸うと、目を細めて冷たく言い放った。
「スグ、学校へ行きなさい。もう予定時刻をとっくに過ぎているはずよ」
「モミ、あたしは……」
「行きなさい。私は、やるべき事を全うしない人間とは話したくないわ」
「……うん、分かった。ごめんなさい」
さっと顔ごと視線が外された。一言も発さないまま、背を向けて部屋から出て行く。
バタン。その乾いた音が、この空間を淡い光から完全に切り離した。途端、重い空気が体に圧し掛かってくる。
――――私は、先へ進まなければいけないのだ。
大多数の人間と大きく考えが違っていようが、私には関係ない。奇妙に見られても、疎まれても、嘲笑されても、私は別に構わない。何とでも言えば良いのだ。
机の隅に置かれた黒いノートパソコンを見やる。自由に動けなくなった私のために、両親が買い与えてくれたものだ。元々インターネットにはあまり興味が無かったが、せっかく気を使ってくれたのだからと、私はネットで色々な情報を見るようになった。
そうしてしばらくたった頃、あるゲームの名前を再び目にしたのだ。
剣の世界――――≪ソードアート・オンライン≫。
それは、私がモンスターのデザイン案を提供したゲームだった。
ゲームなどには一切見向きもしない私だが、この時は違った。忌々しい出来事も思い出すことになったが、どんな作品に自分のイラストが使われたのか気になり、ゲームの紹介をしていたブログのリンクから公式ホームページへ飛んだ。
そして私は、衝撃を受けた。
この世界の中で、生活出来るということに。
――――“生きる”ことが出来るということに。
生物学上、私は生きている。けれどもう、私にとってこの体は死んだも同然だったのだ。
川に落ちた一枚の葉のように漂い、いつか朽ちるのを待つ存在。
私の事を支えようとしてくれた人はもちろんいた。しかし、存在しても良い場所も、自身の価値も見出せなかった。
……けれど、この世界に行けたらどうなのだろう。
モンスターを狩って生活し、家を持ち、釣りをし、畑を耕す――――。そんな日々を過ごすことが出来る。
ある程度のルールはあるが、それはこちらだって行動を制限するものはいくらでもある。それを考えれば、この世界は遥かに自由なのだ。
ならば、自分の価値を自分で作り上げることが出来るのではないか。
自分の脚で歩いて、走って、跳ねることが出来るだから。何物にも、私は縛られないのだから。
――――もし、この世界を“もう一つの現実世界”に出来るなら。
時間だけが浪費するように進むなかで、置いて行かれた私が先へ進めるなら。
私は、もう一度生きることが出来る。この世界で死んだのなら、そちらの世界の住人になればいい。それで私が生きることが出来るのなら、……たとえニセモノだらけの世界だとしても構わない。
ただ、これの意味することはすなわち、今の世界で“生きる”ことをやめるということなのだ。しかしすでに私自身が、今生かされている世界を拒絶している。
もちろん、スグや幸歌、伸一の顔が浮かばなかったわけではない。だが、迷うことはなかった。
たとえ“もう一つの現実世界”から“己の生きる世界”と認識が変わり、破滅への一途をたどったとしても、後悔はしないだろう。
そもそも、すでに私は毒針の道を進んでいるのだ。多種多彩な花が咲き、光り輝いている道はもう踏み外しているのだ。
今以上の暗闇に突き進んだとして、何が変わるのだろうか?
≪ソードアート・オンライン≫の予約は無事に済んでいる。あとは数日後に届くのを待つだけであった。
心躍る、なんていうことは特にない。ただその日を待つだけだ。
小ぶりのバックを膝の上へ乗せ、車椅子の車輪の外側に付いたハンドリムを操作する。私の部屋は1階へ移動させてもらったので、部屋の外に出れば玄関は目と鼻の先だ。
――――なんだけれども。
私の動きは、自然と止まった。
「……あ、紅葉」
玄関の方向から歩いてきた人物もこちらに気づき、私の名前を呼んで足を止めた。
……そう、玄関に近いということは、それだけ“彼”と鉢合わせをする確率が上がるし、引き返すことも出来ない。
私はろこつに嫌な顔をして、わざと見せつける。
「2人の時にその呼び方はやめてって言っているでしょう?」
何か言葉が返ってくる前に、ドスを利かせて刺々しく言ってやった。
「――――和人さん」

「……ごめん、紅葉さん」
もともと逸らされていた視線が、さらに落ち込む。私は口に馬鹿にするような笑みを作り上げると、ハンドリムを操作して和人の方へ近づく。彼の肩が、少しだけ揺れた。
「恐れ入りますが、そこを通して頂けませんか?」
「あ、ああ、ごめん。……ごめんなさい。あの、手伝おうか?」
「いいえ、結構です。慣れていますので」
彼の体が脇へ逸れたのを確認して、車椅子の操作を再開した。だが和人とすれ違った瞬間、声が掛けられる。
「いつものとこに行くのか?」
「あなたには関係のないことだわ。……いつも言っているでしょう。私に関わらないでいいですから」
私は嫌悪に顔を潜めながら、冷たい声で素っ気なく言い放つ。
痛いほどの静寂が包んだ。
この空気を作っているのは私だと、十分理解している。けれど破ろうとは思わない。
背後にいる和人の様子はもうわからない。……といっても、彼はいつものように目を逸らして、顔を俯けているだろうから、分かるはずもないのだが。
怒りか、悲しみか、はたまたそれ以外の感情か。
私には、もう確認する術はない。
だがどんな感情を抱いているとしても、もう関係ないのだ。
私は追い打ちをかけるべく、必ず傷つくと分かっている言葉を投下する。どんな事よりも、苦しいものと知っているから。
「本当の兄じゃないくせに」
これ以上の会話は時間の“無駄”だ。
さらに反応が返ってくる前に手早くハンドリムを操作した。玄関付近で車椅子の車輪に付けたカバーを外す。そして感情が出ないように玄関のドアを開け、そっと、けれど後ろは振りかえずに閉めた。
私の後を追いかけてくるものは、当然のことながら誰一人としていなかった。
――――しかし、門を出たところで待ち構えている者はいた。
「あら……、伸一じゃない」
全く予想していなかった人物に、私は目を丸くする。それは向こうも同じだったようで、人の家の前で何やら難しい顔をしていたくせに、ビクリと小動物のように跳ね上がる。
「も、紅葉ちゃん」
「そんな、まるで幽霊でも見たみたいな反応をしないでちょうだい」
「ご、ごめん」
しゅんと肩を落とす彼に、私は表情を柔らかくした。尖っていた感情が、雪解けのように穏やかになっていく。
「まあ、いいわ。……それで、ウチに何の用かしら。あいにくだけど、スグは部活に行ったわよ」
「そ……っ、そんなんじゃないよ!!」
顔を真っ赤にさせて間髪入れずに言い返してくる伸一に、私は苦笑いを作った。
「あなた、まだスグと話せていないのね」
「う、うぐっ……」
声を詰まらせたかと思うと、彼は明後日の方向を見て、
「……いいんだよ、見ているだけで」
「同じようなことを、もう何年も言っているわよ?」
「うう……」
ついからかってやると、拗ねたように口を尖らせる。彼は気づいていないが、私や幸歌以外にはこんな表情はしない。微笑ましくなり、私は笑みを浮かべる。
「伸一のことを信頼しているから言うけれど、出来るならあなたにスグを守ってほしいわ」
「へ? どうして」
「スグは、私にとって大切な人のうちの一人よ。そう思うのは当然だわ」
「そ、そうじゃなくて。……どうして僕なの?」
本当に分からないようで、伸一が間の抜けた顔で私の目を見詰め返してくる。私は小さく息を吸った。
「……私が今心から信頼しているのは、幸歌と、スグと、……伸一だけだもの」
「ええっ!?」
「どうして驚くのかしら。当たり前じゃない」
伸一が唖然とした表情で、口をパクパクと開閉させている。思わずクスクスと笑うと、彼はフリーズから立ち直ったのか、頬を赤くさせたまま頭をガシガシと掻き、
「紅葉ちゃんってさ、よくそういう恥ずかしいこと言うよね……」
「どうして恥ずかしいのよ。本当のことじゃない。嘘は言っていないわ」
「分かってるよ! ……だから、余計恥ずかし――――ああ、もういいや」
「何よ、はっきりしないわね」
口元を手で押さえてそっぽを向く伸一に呆れ、眉をひそめる。だが、同時に違う可能性が頭の中に浮かんだ。
「それとも、あなたにとって私のこの気持ちは重いのかしら」
刹那、伸一が顔を上げる。ギョッとしたような顔だった。彼は私が口を挟む間もなく早口で、
「そんなことない! 嬉しいよ。……僕も、紅葉ちゃんは大切な友達だって思ってるんだから!」
「……そう。ありがとう、私も嬉しいわ」
――――人間とは残酷で、嘘をつく生き物だ。どんなに正しさを貫く人物でも、自己中心的になる時はある。聖人のような人などごく一部だ。すなわち、『清く正しく、どんな人に対しても差別せずに優しく』などほぼ不可能だと言ってもいい。
しかしそれでも、目の前にいる彼は、少なくとも私にとっては“優しい人”だ。
確かに教室に通っていた頃と比べれば、伸一とは少し疎遠になっただろう。けれどもこうして会えば対等に接してくれるし、私も躊躇いなくそう出来る。
“普通”に話してくれる数少ない友人だ。
「……そうだ、伸一。これから幸歌と会う約束をしているのだけれど、あなたも来る? きっと幸歌も喜ぶわ」
「う、うーん……」
「この後何か予定でもあるのかしら」
「そ、そういうわけじゃないんだけど……」
「それだったらいいじゃない。もう少し伸一と話したいわ」
思案する表情になる伸一を見詰める。彼は目を泳がせたが、やがてコクンと一つ頷いた。
「じゃ、じゃあ……」
「決まりね。さ、行きましょ?」
伸一が私の横に並んだのを確認して、ハンドリムを操作し始める。はじめ彼は歩幅を小さくし歩行スピードを緩めようとしてくれたみたいだが、車椅子の操作に慣れた今となっては一般的な人が歩く速度とそう変わらない。彼の優しさに感謝しつつ、私たちは進む。
「そういえば、伸一。この前駅でバレエ教室の先生にお会いしたのだけれど、あなた教室をやめたんですってね」
「……うん、やめたよ」
「……どうして、と問い詰めたりしないわ。何をしようが伸一の勝手だもの。けれど」
「そんな深い理由はないよ。ただ……」
「ただ?」
一瞬黙り込む彼だったが、意を決したように口を再び開く。
「僕さ、たとえクラスがバラバラになってしまっても、3人で夜の帰り道を歩けるのが楽しかったんだ」
「……そうね。“私”も楽しかったわ」
「うん。――――紅葉ちゃんがバレエの楽しさを教えてくれた。……幸歌ちゃんが、躍ることの嬉しさを教えてくれた」
あの頃の時間は、色鮮やかだった。
私もそれを思い出して、軽く目を閉じる。
「紅葉ちゃんはいつも凄く厳しくて怖かったけれど、紅葉ちゃんがバレエを大好きなのはよく知っていたから、僕も精一杯頑張った。……たとえ上手く出来なくても、頑張ること自体が凄く楽しかったんだ」
伸一が立ち止まった。見上げれば彼の目はユラユラと切なげに揺れていて、私は何も言えなくなる。
「けれど幸歌ちゃんは引っ越して行ってしまって、紅葉ちゃんは……バレエが出来なくなってしまって、僕があの教室にいる意味はなんだろうって思って」
「それで……、やめてしまったの?」
「……うん、そうだよ」
……これはきっと、彼の優しさ。弱さ。
細い息が自身の口から漏れ出る。眉を八の字にしながら言葉を探し……、しかしどう言えばいいのか分からなった。
私は押し黙ったまま、ハンドリムの操作を再開した。知らず知らずのうちに、ポツリと言葉が漏れ出る。
「馬鹿ね」
それを聞いた伸一も泣きそうな表情で苦笑いを浮かべ、
「ごめん」
震えた声だった。深い、深い、暗い底を覗き込んだような、悲しみを孕んだ声音だった。
「本当、馬鹿だわ……」
「うん。知ってる」
「もう……」
私は瞑目し、――――しかしすぐに目を開けた。
「でもね、私、あなたのそういう所も嫌いじゃないわ」
伸一が両目を見開く。私は何も言わずに笑みを作り、彼から目を外して前を見据えた。
*
駅から一番近い大きめの公園。時刻は14時をちょうど刻んだ頃だ。
滑り台や鉄棒の周りでは小学校低学年の子どもたちが笑い声を上げながら走り回り、広い砂地では親子がキャッチボールをしている。
賑やかで穏やかな空間だ。私は口元を緩ませる。
視線を巡らせれば、大きな木の下に設置されたベンチに人影があった。読書中で顔は俯けられていたが、雰囲気は全く変わらない。今日会う約束をしている幸歌だ。ピンク色のワンピースを着ている。
私は伸一と顔を見合わせると、ゆっくり近づいて声を掛ける。
「久しぶり、幸歌」
少女の顔が上がる。ふわりと髪が風に舞った。
「あ、久しぶり紅葉――――って」
私の顔を見て笑った幸歌だったが、背後に立つ伸一を見て動きを止めた。ボンッと小さい爆発が幸歌の顔で起きる。顔をゆでダコのように真っ赤にさせ、ガバッと勢いよく立ち上がった。
「な、なななななな、何で長田君が……っ」
「あら、駄目だったかしら。来る途中で会ったから、せっかくなら3人で、って思ったのだけれど」
「ううん、別に駄目じゃなくて……、むしろ……う、うれし……」
「幸歌?」
「何でもない!」
ブンブンと顔を横に振ったかと思うと、両手で顔を覆ってトスンと再びベンチに沈んだ。本当に幸歌は可愛い。
一方、その様子を伸一はきょとんとした表情で見ていて、何も分かっていないご様子だ。さすがに呆れてくる。私は眉を吊り上げながら、肘で彼の脇腹を小突いた。
「なっ、何、紅葉ちゃん」
「別に何でもないわ」
私は大きなため息をつき、幸歌の細い肩に手を置いた。
「幸歌、驚かせてごめんなさい」
「ううん、ありがと……」
手を退けた彼女は、ふにゃりと笑う。桃色に染まった頬が愛らしい。
あいかわらず彼女の笑顔は朗らかで優しかった。柔らかな声が、耳によく馴染む。
彼女も今までと変わらない視線を向けてくれる一人だと、そう素直に思える。
「ごめんね。大変だったでしょ」
「いいえ、大丈夫よ。そもそも、今日も外へ出るつもりだったから」
「そう? ……あ、長田君も、ええと、ありがと」
「い、いや……」
チラリと視線を向けられた伸一が、ぎこちなく言葉を返す。幸歌もあちこち目をやり落ち着かない様子だ。だが、ベンチの横に置かれた紙袋を見た時、「あっ」と短く声を上げる。
「そうそう! 今のうちに渡しておかなきゃ」
きっとどこかの雑貨屋でラッピング用のものを購入してきたのだろう。パステルブルーのチェック柄が可愛らしく、幸歌らしい。
彼女は高らかに手を打つと、宝物を手にするかのような手つきでその紙袋のヒモを掴む。そして私に向かって差し出し、
「はいこれ、お祝い!」
いきなりのことで私は面食らった。咄嗟に言葉が思いつかない。
「……え、お祝いって、まさか」
「そうそう、そのまさかだよ。直接渡したかったから、半年以上遅れちゃったけどね~」
「……合格? ……って、何? 紅葉ちゃん、何か資格でも取ったの?」
すると、ただ一人状況を飲み込めていない伸一が首を傾げて問うてくる。幸歌は目を丸くすると、私の顔を凝視して、
「紅葉、長田君に話してないの!?」
「ええ。……だって、わざわざ言うようなことでもないでしょう?」
「そういう問題じゃないよ~……」
呆れたような声を出すと、ガックリと幸歌が肩を落として脱力した。私はどうしてそんな反応をされるのかよく分からず首を傾げる。
「な、何なんだよ。早く説明してよ」
我慢の限界になったのか、伸一が急かした。幸歌にチラリと目配せすると、彼女は諦めたように苦笑いをし、
「ほら、3年くらい前に外国の教育方法を取り入れるってことになって、飛び級制度が日本にも出来たでしょ」
「……あ、ああ、そういえばそんな制度が出来たような――――って、それって!?」
「そういうこと!」
幸歌はまるで自分の事を自慢するかのように胸を張り、
「紅葉は小4の秋に一回目の試験を受けて、ええと、……何年生に進級したんだっけ」
「中学2年生よ」
「そうそう、中2!」
さらっと補足をすれば、幸歌は笑顔で両手を打った。
「……あ、だから紅葉ちゃん転校しちゃったのか……」
3年の時を経て知った真実に、伸一が遠い目をして深く息を吐き出す。それを見た幸歌が一瞬つらそうな表情をしたが、すぐに消し去り、
「それで去年二回目の試験を受けて、また合格したんだよね。国立大学の1年生だっけ」
「ええ。理学部物理学科に入学したわ」
「ひ、ひえー……」
「もうさ、私より3つも学年が上だなんてヒドイよね~」
「そんなこと言われても……。今打ち込めるものと言ったら、勉強くらいなんだもの」
「だからって、そんなに頑張らないでよ~」
幸歌は、ぷぅと頬を膨らませながらそう言った。そんな彼女を見て、一瞬、私は思う。
――――優秀な成績を残したら自分の価値を見出せるのではないかと考えていた、と言ったらどんな表情をするのだろうと。
そしてもっとも大きな理由として、勉学は“私”が一番嫌いなことだったから一生懸命やっている、なんて教えたら……と。
けれど、その考えはすぐにそれは打ち消した。判断時間にして、ほんの数秒。その速さのおかげか、幸歌と伸一が気づいた様子はない。
私はほっとしながらも、表は崩さないように笑顔を作った。
「あ、そうだ、二人に相談したいことがあってね……。見てほしいものがあるのんだ」
幸歌は言うやいなや肩掛けのバックを探り始めた。彼女はおっとりとした性格の女の子だが、同時におしゃべり好きの面もある。私から話題を振ることはあまりないが、話題が絶えることはない。
私は笑みを作りながら見守っていると、やがて幸歌は目的のものは見つけたようで、パッと顔が明るくなった。再びこちらを見てにっこりと笑う。
うすいピンクの花が舞っているメモ紙を手渡された。そこには、何かのグループの名前なのか、数個箇条書きで書かれていた。
「……ええと、幸歌? 何かしら、これ」
「うん。実は私、高校でパソコン部に入っているんだけど……」
「パソコン部? 幸歌が?」
思わず聞き返した。途端、幸歌が「しまった」とでも言うような表情になる。
「あ、えっと、友達のお兄さんに誘われて……」
「……私、てっきり声楽部とか合唱部に入ったものだと思っていたのだけれど」
あの夜の約束を思い出す。
必ずそれぞれの夢を叶えよう、と誓い合ったあの日を。
私はそのすぐ後に不可能な未来へと変わってしまったが、幸歌は叶えるチャンスがあるはずなのに。
「幸歌、部活だって重要なアピール場所よ。それなのに……」
「そ、それは……」
幸歌が今日初めて目をそらした。同じだ、と咄嗟にその言葉が頭に浮かぶ。
何と、と考えるまでもない。引っ越す事を告げたあの時の表情とそっくりなのだ。
嫌な予感がした。ピリピリとした感覚が電流のように走る。私はすぐさま問おうとしたが、それとほぼ同時に、
「――――あ、あの、紅葉ちゃん!」
伸一が大声を上げて割り込んできた。幸歌が目を真ん丸にさせる。私も突然のことに驚き、言葉を失った。けれどもすぐに気を取り直し、
「伸一、何かしら。今大切な話をしているのよ」
「だ、だけど」
「それともあなた、何か知っているのかしら」
「……な、何も知らないよ」
「そう?」
スッと目を細める。伸一は身を固くさせ、幸歌はオロオロとした様子で私たちの顔を交互に見ていた。誰一人として何も言わない。
子供たちの笑い声が、急に大きく聞こえだした。ザアザアと、葉の泣く音が私たちの間を流れていく。
私は深くため息をついて、知らず知らずのうちに入っていた体の力を抜いた。
……何をしているのだろう、私は。
幸歌がどんな部活を選ぼうが、彼女の自由だ。どんな将来を夢見て、どんな道を選ぼうが自由だ。
人は変わる。……変わらない人などいない。
当たり前のことだ。
幸歌も、伸一も、みんな変わっていく。私自身が良い例ではないか。
歌を歌っていてほしいなど、己の願望だ。それを押し付けるなんてどうかしている。
「……ごめんなさい、幸歌」
「え?」
「伸一にも謝らなければいけないわね。……ごめんなさい」
二人に頭を下げた。伸ばした黒髪が肩からさらさらとこぼれ、私の視界に影を落とす。
「ちょっ、ちょっと、紅葉ちゃん! 謝らないでよ!」
「そうだよ! 私、全然気にしてないから!」
「いいえ、そういうわけには……」
「大丈夫だから、本当に!」
「え、ええと、――――ほら、幸歌ちゃん、相談事って何?」
「……あっ、うん!」
伸一が無理やり話の路線を変えた。幸歌がワタワタとしながらも話し出す。
「じ、実はね、部活の人たちでオンラインゲームをすることになったんだけど……」
「うんうん」
伸一が相槌を打つのを聞いて、そっと顔を上げた。すると、二人はホッとしたような色を顔に浮かべる。
「……それでね、すぐには作れないらしいんだけど、ギルドっていうやつを作ろうと思っているの。これが名前の候補なんだけれど、なかなか決まらなくて」
「あー、ギルドか。確かに名前決めは悩むかもね」
己の手の中にある紙に視線を落とす。
ギルド――――事前にゲームについて調べた時に出てきたワードだ。確かチームのようなものであった気がする。……とすると、たしかにこれらの案は少し微妙かもしれない。高校名が入っていたり、個人の名前らしきものが入っていたり……、これは駄目でしょうと、つっこみたくなるものまである。
しかし、少々呆れながら視線を下に滑らせていくと、目に留まったものがあった。思わずそれを凝視し、気づいた時には声も出ていた。
「≪月夜の黒猫団≫…?」
何か惹かれるものが、この名前のそこかしこにあった。
そろそろと紙からゆっくり顔を上げる。瞬間、幸歌の表情を見て確信した。けれど、確かめる言葉が口から滑り出る。
「もしかして……、あの時の猫のこと?」
「あ、やっぱり分かった?」
「ええ。少し驚いたけれど。……ねえ、リュヌは元気かしら」
「元気すぎて困っているくらいだよ」
あはは、と幸歌は笑う。けれどもすぐに神妙な面持ちになり、少し眉を下げながら心配そうに言葉を発した。
「……ごめん、嫌だった?」
事故に合った日と同じ日だから、と続けなくともそう言いたいのが分かった。だから私は、否定の意をこめて静かに首を横に振る。
「いいえ。……むしろ、嬉しいわ。思い出を大切にしてくれているって分かるもの」
「そ……、そう?」
「ええ、もちろん。……じゃあ私、≪月夜の黒猫団≫に1票を入れるわ。可愛い名前だと思うから」
「ほ、本当!? よかった!」
再び幸歌の周りにコスモスの花が舞う。それは優しい色の花びらで、まぶしさに目が眩みそうになる。けれど私は視線をそらさず微笑みを作りながらその姿を見て、静かに聞いた。
「ところで、そのゲームの名前は何なのかしら」
「≪ソードアート・オンライン≫っていうゲームだよ。今結構テレビとかで騒いでいるやつ!」
「ああ、知っているわ。……それにしても、偶然ね。実は私もやろうと思っているのよ」
「そうなの? 紅葉がゲームだなんて珍しいね。……あ、自分のデザインしたモンスターが気になるとか?」
純粋な質問に、一瞬言葉が詰まった。
“珍しい”。
確かにそうだ。私自身でさえ少し前の己を思えば、そんな道楽に身を投じるなんて奇妙に感じてしまうのだから。……けれど、 “もう一つの世界にしたい”、なんて口が裂けても幸歌には言えない。
ただ純粋に“ゲーム”を楽しもうとしている、彼女には。
……真っ白で美しい輝きを放つ彼らを、醜い色で染めてはならないのだ。
私はぐっと体に力を込める。口にすることは許されないと叫ぶ理性が、ギリギリと“自身”の身を縛り上げた。
ギリギリ、ギリギリ。
かつて“私”を落下から助けた3本の糸が、自重で食い込む。タラリと、どす黒く熱い液体がこぼれた。あちこちから止めどなく溢れ出る液体と混じる。
ボタボタ、ボタボタ。
ぐらぐら、ぐらぐら。
上も下も右も左も見えない暗闇。熱さが肌を少しずつ焦がし、寒さが体を鋭く突き刺す場所。そこで宙ぶらりんの状態になっている“私”。
口元を綻ばせた。愛しい姉や友人の顔を思い浮かべながら、糸を自らの手で断ち切る。
「――――ええ、そんなところよ」
落ちる、落ちていく。
……いや、一滴の白すら垂らされていないような黒の中では、その感覚でさえ失われていた。
落ちているのか、底まで来たのか、それともすでに底に居たのか。
もう、分からない。
己の手すら視えない。
そして、誰も“私”が居る場所を知らない。
「……伸一は?」
「へ?」
ゆらゆらと揺れる思考を押しとどめ、数秒の間を置いた後、伸一の方へ顔を向けて尋ねた。間抜けな声が上がる。私はその反応に苦笑いをし、
「だから、あなたは≪ソードアート・オンライン≫をやらないの?」
「あっ、それは……」
何気なく聞いたつもりだったのだが、何故かチラリと幸歌へ視線を送る。彼女も伸一のそれを受け、気まずそうに俯いた。
その意味ありげな視線での会話を、不思議に思って首を傾げる。
「どうしたの? 何かおかしな事でも言ったかしら」
「う、ううん。そういうわけじゃないよ」
「そう?」
「うん。……それで≪ソードアート・オンライン≫だけど、僕は落ち着いてから始めようかなって。買うのが大変そうだから」
「あら、珍しいじゃない。あなたがこんな話題になっている新作に飛びつかないなんて」
「親が勉強しろって五月蠅くてさ」
「……なるほど」
それならまあ、納得出来る。スグも中学に上がってから苦手な教科では苦戦しているようで、何度勉強を教えたことか。
「二人はプレイヤーネームもう決めたの?」
「ええ、決めてあるわ」
「うん、私も!」
「幸歌は≪サチ≫、かしら?」
「……え! 正解! なんでわかったの!?」
「ふふ、何でかしら?」
「もう! そういう紅葉は何にするの?」
「“Kika”って書いて、≪キカ≫にするつもりよ」
「キカ?」
伸一と幸歌が同時に声を上げた。
「……え、どうして≪キカ≫なの?」
「“Momizi”に“K”なんて入ってないし……」
「ふふふ、秘密よ。……でも、一つ目の理由はすぐ分かると思うけれど」
もう一つの現実世界での名前――――、それは変えることが出来ないらしいし、ずっと使っていく大切な名前だ。だから、私はそれに“Kika”を選んだ。
理由は2つ。
一つ目の理由は、私にとっては掛け替えのない、輝いている思い出の象徴から取った。それはとても大切で、絶対に失いたくないものだ。だからこそ、“もう一つの現実世界”にもその欠片だけでも持っていこうと思ったのだ。
そして二つ目は、私自身が己に科した戒め。この名を呼ばれるたびに痛みを感じて、決して許されない罪を思い知るために。
……とまぁ、二つ目はともかく、幸歌ならきっと一つ目にはすぐに気が付くはずだ。と思っていたのだけれど。
「ええ!? うそ……何? 何かの単語? フランス語とか?」
「さぁ、どうでしょう」
本当に分からないらしく、うんうんと頭を押さえて唸りだした。その姿に心が和む。
続いて伸一の方を見ると、手を顎に当てて考え込んでいた。もしかしたら彼は気づくかもしれない。
「うーん、じゃあ、ゆっくり考えてもらおうかしら。……ちなみに、理由は2つあるわよ」
「もう、いじわるだなぁ。……いいよ、後で辞書使うから」
「頑張ってください」
澄まして言えば、幸歌がむうと頬を膨らませた。まるでハムスターか何かのようだと思いながら見ていると、彼女がぷっと吹き出して笑い出す。伸一もそれに釣られたのか、笑顔を浮かべた。
「あ、ねえねえ、紅葉! ……ううん、キカ! 私たちのギルドに入らない!?」
「ギルドって、……さっき話していた≪月夜の黒猫団≫?」
「そう! みんないい人たちだよ! きっと仲良くなれる。私からみんなにお願いするからさ。……ね、どうかな?」
そう笑顔で誘ってくる彼女を、どこか遠い気持ちで眺めた。
――――幸歌と同じギルド。
それはとても魅力的に感じられた。きっと、幸歌やその友人と共にとても素晴らしい時間を過ごすことが出来るだろうと確信できたからだ。
私は俯き、唇を噛み締めた。
「……とても嬉しい話だけれど……、ごめんなさい。遠慮させてもらうわ」
先ほど再認識したばかりなのだ。私と彼女たちの目的は明らかに違う。どう解釈したとしても幸歌たちのまっすぐな線とは交わることはない。
スタート地点から違うもの同士が真っ向からぶつかれば、どうなるかは目に見えていた。人間関係なんて、少しのすれ違いで、ほんの小さなヒビで、粉々になって跡形もなくなってしまう。どんなに仲がよくても、所詮硝子細工のように脆いのだ。
どちらも“リアル”での友人。優しい幸歌なら選び取ることが出来ず、板挟みになってしまうだろう。
そもそも、私がいつかギルドに入る時がきたとしたら、間違いなく “現実世界”で全く交流の無い人にする。……むしろ、そうでなくてはならない。“桐ケ谷紅葉”を知る人物が、一人でも居てはならないのだ。
「ごめんなさい、幸歌」
再度軽く頭を下げて謝る。ぼうっとしていた様子だった彼女は、慌てた様子で顔の前で両手を振り、
「だ、大丈夫だよ! 私もいきなり過ぎたかなって思っているし、気にしないで!」
「そうそう、そういう事はゲームの中でも相談出来るだろうし! 今はとりあえず、保留ってことにしておけば? ≪SAO≫にログインしたら気が変わるかもしれないし」
「……ええ、そうね」
私の思考は露知らず、二人はまた笑って「気にしないで」と言う。
申し訳なさが、胸を締め付けた。
「――――そういえば、紅葉、時間は大丈夫なの? どこか行くって手紙に書いてなかったっけ」
「……あ、ああ、もうそんな時間になってしまったのね」
幸歌に聞かれて時刻を確かめれば、確かにもうそろそろ移動しなければいけない時間だった。子どもの人数が、先ほど見た時よりも増えている。
元々そんな長い時間会う約束では無かった。幸歌がこちらに寄ると言うので、電話で急遽交わした約束だったのだ。……ただそれが分かっていても、名残惜しい雰囲気はもちろんあった。幸歌も何か察した様子の伸一も、浮かない顔をしたので、私は思わず、
「良かったら二人も来る? ここからすぐ近くにあるから」
「……え、でも大丈夫なの?」
「そもそも紅葉はどこに行くの? 手紙でも電話でも、何も言ってなかったよね」
「児童養護施設よ。小学生に勉強を教えるボランティアをしているの。……本当は私の年齢では出来ないのだけれど、施設長の方が母の知り合いらしくてね。掛け合ってくれたらしいわ」
「……そういう施設ってさ、僕みたいな無関係の人間が行くのは難しいんじゃない?」
伸一が渋るような顔つきになった。幸歌も眉を寄せて、困ったような顔になる。
「そうね。……なら、私が今から電話してみるわ」
「う、うん」
やはり私も、少しでも長く二人と一緒にいたいという心理が働いているようだ。素早くハンドリムを操作しベンチから離れると、スマートフォンを鞄の中から取り出す。迷うことなく施設の電話番号へコールした。程なくして電話が繋がる。
『はい、弥栄学園でございます』
「私、学習ボランティアに参加している桐ケ谷紅葉と申します」
『ああ、紅葉ちゃんね。どうしたの?』
「実は――――」
手短に幸歌と伸一の事を話す。彼らがいかに真面目で、優しい性格であるかということも。
「どうだった?」
数分の通話を終え二人の元へ戻ると、すぐさま緊張気味な表情で声を掛けられた。私は笑みを作り、
「明日、11月生まれの子たちのお誕生日会があるそうなの。だから、その買い出しと準備のお手伝いをしてください、だそうよ」
「じゃあ、もう少し紅葉と居られるんだね!」
幸歌が満面の笑みを浮かべる。伸一もどことなく嬉しそうな顔だ。
「よし、紅葉行こう! 早く!」
「もう、そんなに急がなくてもいいでしょう?」
「え~」
「じゃあ僕、紅葉ちゃんの車椅子押そうかな」
「伸一までそんな事言って……。大丈夫よ、一人で出来るわ」
「遠慮しないでよ」
「遠慮なんかしていないわ。伸一にやられると怪我しそうで怖いから言っているのよ」
「ひ、ひどっ」
「あははっ、紅葉~、照れてるの?」
「照れる? 私が? どうして伸一相手に照れなければいけないのかしら」
「……紅葉ちゃん、僕もうそろそろ泣きそうだよ」
ボソリと伸一が呟くと、耐えかねたように幸歌が吹き出した。彼女は目元に浮かんだ涙をぬぐい、
「ね、今度さ、3人でどこか行かない?」
「あ、いいね!」
ゆっくり、ゆっくり私たちは進む。何だかんだ言いつつも、私は伸一に車椅子を任せていた。
「じゃあさ、水族館はどう?」
「……そういえば、来月リニューアルオープンする所があるって聞いたけれど」
「そうそう、そこ!」
「へえ~、いいねぇ! 私、水族館は久しぶりかも」
「あ、そうなの? じゃあ、冬休みにみんなで行こう!」
伸一が車椅子を押す手を止めた。その代りに、右手の小指を私たちに向かって出してくる。すぐに彼の意図を汲んだ幸歌が、その指に自身の指を絡ませた。
「ほら、紅葉も!」
「……まったく、この歳にもなってゆびきり?」
呆れた言葉を返しつつも、私も指を絡めた。
「「「約束」」」
今度こそは、絶対に。
何故かそんな言葉が頭の中に生じた。
*
木々に囲まれた児童養護施設。
カラフルな鉄棒や滑り台を横目に通り過ぎ、正面玄関の裏にある職員用の玄関から中へ入る。
「お姉ちゃん! 紅葉お姉ちゃん!」
「みんなーっ、お姉ちゃんが来たよ!」
今か今かと待ち構えていた様子だった女の子二人が声を張り上げる。バタバタといくつもの足音が楽しげな笑い声と共に近づいてきて、瞬く間に周りを囲まれた。
「みんな、走ってはいけないわよ。危ないわ」
「大丈夫だよ!」
突進してきた子どもたちにそう注意すると、小学4年生の男の子が歯を見せて笑った。私も「仕方がないな」と思いつつも、笑みを浮かべる。
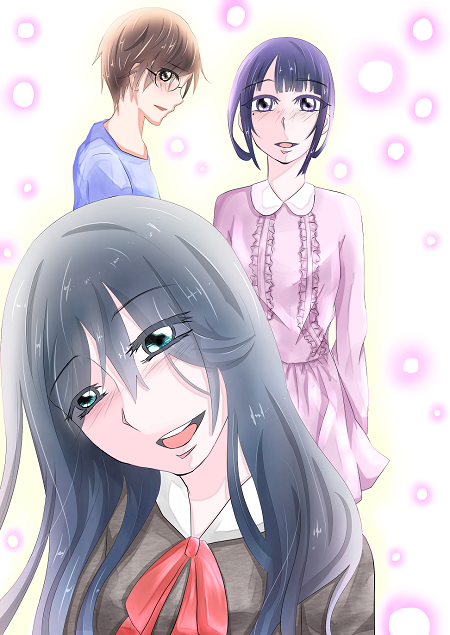
「紅葉ちゃん、凄い人気者だね」
「いつもこんな感じなのよ。どうしてかしら」
「紅葉が優しいからに決まってるでしょ!」
間を置かずに幸歌にそう断言されたが、あまり納得は出来なかった。飲み下せず、もやもやとした感覚を残す。
優しい? 私が?
こんな冷酷な私を、優しいと形容してみ良いものなのか。私より、幸歌や伸一の方が断然優しいと思うのだけれど。
私は思わず後ろを振り返ろうとする。だがその行動は、視界に飛び込んできた何色もの折鶴に阻まれた。
「……え?」
「お姉ちゃん、これあげる!」
差し出しながらニコニコと笑うのは、私がいつも担当をしている女の子だ。戸惑いながらも、それを受け取る。
「これ……、千羽鶴じゃない。どうしたの?」
「えへへ、みんなに手伝ってもらったの!」
体と羽のバランスが悪いもの、頭と尾が捻じれてしまっているもの……、形はけして綺麗とは言い難いものが多かったが、それらは間違いなく折り紙で出来た鶴だった。全く予想していなかったものを渡されたことに驚き、言葉を呑む。
一体、どれだけの時間をかけて折ってくれたのだろう。
……そして、一体何をこの子たちは祈ったのだろう。暑くもないのに、手のひらがじっとりと汗ばむ。声が震えそうになるのをなんとか堪えた。
「大変だったでしょう?」
「ううん、そんなこと無かったよ!」
「前にお姉ちゃんが折鶴の折り方を教えてくれたから、お礼に渡したかったんだ!」
「これで、きっと紅葉お姉ちゃんの脚も治るよね!!」
――――嗚呼。
私は静かに両目を閉じた。
子供たちの真っ直ぐで穢れの無い願い。他意など無い願い。
けれどこの両脚は、願ったところで治らないのだ。描いた夢は塗り潰されたのだ。
願っても、“無駄”なのだ……。
「……紅葉さん、ごめんなさい」
すると、重い足取りで奥から歩いてきた少女が、辛そうな表情で私に謝罪をしてきた。私より3つ年上の紀子さんだ。その向こうには、同じような顔をした中学生や高校生の人たちが立っている。
「私たちや先生たちが説明したのですが、分かってもらえなくて……」
「紀子ちゃん、どうして謝ってるの……?」
「そうだよ、別に悪いことはしてないでしょ?」
紀子さんや彼女の後ろの人たちの顔がますます暗くなっていく。私は、そんな紀子さんたちを安心させるように微笑みを作った。
誰も悪くない。悪くは無いのだ。
脚が治るようにと願った幼い子供たちも、理解させることが出来なかった紀子さんたちも。
「ありがとう、嬉しいわ。大切にするわね」
「本当? 部屋に飾ってくれる?」
「ええ、もちろんよ」
子供たちの頭を優しく撫でる。一体、どれほどの痛みをこの小さな体で受けたのだろう。一体、何度夜を泣いて過ごしたのだろう。
私には、推測することしか出来ない。実際に苦痛を受けた者にしか、理解など出来ない。
だから私は、せめて彼らを受け止める。それが、私に出来る最善のことだと信じているからだ。
「紅葉お姉ちゃんのこと大好きなの?」
後から様子を窺っていた幸歌が、そう子供たちに問いかけた。子供たちは少しも迷う素振りは見せず、
「うん! 大好き!」
「当たり前だろ!」
「紅葉お姉ちゃん、いつも色々な事教えてくれるもん!」
純粋な好意を一斉に向けられた。今まで経験したこともないそれらに、築き上げてきたあの決意が瞬間的にグラリと崩れそうになる。私は咄嗟に顔いっぱいに笑顔を張り付け、何とかそれに耐えた。
「ありがとう。……みんな、本当にありがとうね」
子供たちはエヘへと照れくさそうに笑う。先ほど千羽鶴を手渡してくれた女の子も、両の瞳を輝かせて言った。
「紅葉お姉ちゃん、どこにもいなくならないでね! 約束だよ」
「……ええ、もちろんよ」
どうか、掠れそうになった声に気付かれませんように。
*
私は神も運命も信じていない。
けれども、私が交わす約束とは真逆に突き進むように運命が出来ているのではないかと、本気で思えてくる。
……ここまで来ると、そう考えてしまうのは仕方がないというものではないか。
馬鹿馬鹿しいと一蹴出来なくなってくる。
その日、ゲームの世界はゲームでは無くなった。
憤怒、憎悪、悲嘆、畏怖、焦燥、自棄、絶望、後悔、困惑、諦念……、そんな負の感情が2つの世界を同時に覆い尽くしたのだ。あらゆる者がそれに飲み込まれ、衝撃のあまり言葉を忘れる人々が多くいた。
けれど私はその中でただ一人、笑っていた。周りからすれば、“狂気”として受け止められていたかもしれない。突き付けられた現実に狂ったのだと、そう考えた者もいただろう。
しかし、実際は全く違う。正反対だ。
――――歓喜。
“狂気”ではないのだ。もし言うのならば、“狂喜”であろう。
嗚呼、なんて素晴らしいことだろう!
嗚呼、この身を焦がすような喜びは何と言い表せばいいのだろう!
願いは完璧な形で叶ったのだ!
“もう一つの現実世界にしたい”……、これ以上の形で実現することなど不可能なはずだ。“もう一つの現実世界”を実現させるための策は、これの他には存在し得ないはずだ。
――――否、もう“もう一つの”ではない。この世界は、もはやニセモノではないのだ。
ここはすでに、唯一無二の現実なのだ!
この上なく完璧だった。言うことなど一つもない。
私には到底到達出来ない域にあったものを、彼は――――茅場晶彦はやり遂げてしまったのだ。
全身が震えた。
両手を胸に当て、ただ身を震わせた。背中がぎゅっと縮こまる。
私はひたすら愉悦に浸った。体の中が掻き回されているみたいに揺さぶられる。
こんな風に頭へどんどんと血が上り詰めていくような激しい感情は、覚えている限りの記憶を探っても見当たらない。
逆らうことはせず、感情に身を任せた。狂おしいほどの喜びに、湧き上がるこの世界への愛しさに。
……ああ、愛おしい。この世界が愛おしい。
私は笑っていた。
真っ赤な空を――――ローブを纏う巨大な死神を見上げ、笑っていた。
……笑っていた。
けれど、一つだけどうしても不可解なことがある。
頬に伝うこの涙は、一体誰のものなのだろうか?
ページ上へ戻る最近のテレビは、もうすぐ発売のゲーム―――――≪ソードアート・オンライン≫の話題で持ち切りだ。
……まあいつもの私なら、ゲームなんて無視するだろう。興味なし、と。
けれど、4年前のあの日、私は変わった。……否、変わらざるを得なかった。
――――左足の自由と、右下肢。
それがあの事故で失ったもの。
ただ、右足は神経信号こそは守られたため、今は金属製の義足を装着している。左足に関しては麻痺が残り、動かすことも出来ない。
……これは、バレリーナとしての死を意味する。
今の私には、バレエでのポジションの1番――――両足のかかとの裏どうしをつけ、足の付け根から左右に開いて立つ立ち方――――さえ出来ないのだから。基本中の基本あり、バレエをやっていない人でも出来ることなのにも関わらず。
それでももしかしたら、手の振りだけでも何か表現出来るのではないかと、最初は色々と試していた。
けれど、何かが違う。私がやりたいのは、もっと、もっと全身を使う美しいバレエ。
左足に関してはリハビリ次第で日常生活で支障が無いくらいには回復するだろうと、医者には言われた。だが、それでは意味が無いのだ。
……左足が動かせるようになっても、義足を装着したとしても、あの頃には戻れない。
あの頃のようには踊れない。
ならば、私が存在を許されている場所はどこなのだろう。
“天才少女”であることを望んでいた周囲の者は離れていく。煩わしいくらいに張り付いてきた学校や教室の生徒は影で噂話をしたり、見下すようになった。両親は一見変わっていないように見えても、ふとした瞬間に腫物を扱うように接する。……“天才少女”にポジションを奪われていた人たちは同情するように泣いていたが、その裏では一体どんな声で笑っているのだろう。
……私は悟った。
もう、あの日のように舞うことは出来ない……、つまり、私には何も残っていないと。価値など無いんだと。
バレリーナとしても死んだけれども、あの日、“桐ケ谷紅葉”も死んだのだ、と。
その事実は、あの事故の前と後の周囲の温度差を比べたら火を見るよりも明らかだった。
だから、足掻くことをやめてしまった。……いや、正確に言えば、やる気力すら湧かなかったと言う方が正しいかもしれない。
……それはバレエだけではなく、絵も、演劇も、弓道も。かつての“紅葉”が好きだったものすべてのことに対して、以前のような高揚感が無くなっていた。
頑張るだけ、願うだけ“無駄”だと思ってしまったから。
そして一度気づいてしまうと、延々と意味の無い時間が続く希薄な毎日になった。
何をしても、どこにいても。
いつも『こうじゃない、何かが違う』と誰かが泣き叫んでいた。
鬱陶しいくらいに、いつも、いつも。……その正体はよく視えないけれど。
ふっと、幼い頃によく聴いた童謡が頭をよぎる。まるで池に落ちたドングリみたいだ。山に帰りたいと泣いて、戻れるはずのない場所を望んだドングリみたいだ。
「……はあ」
私は大きなため息をついた。深く、長く、細く。
――――あれから4年の月日が流れた。
残酷で、空虚な、宙に漂うような日々が続いて、こんな所まで来ていた。
ただまあ、車椅子で過ごさなければいけない生活になったとはいえ、部屋に引きこもったりはしなかった。というのも、事故後はスグに無理やり連れ出されるようになったのだ。
『色とりどりの景色を見て、空気を吸って、今しか出来ない経験をしようよ! ずっと家に居たらさ、腐っちゃうよ。あたしがモミの足の代わりになるから!!』
そう言って、スグは私の車椅子を押した。当時小学4年生になったばかりの彼女にそれは重かっただろうに、両親の反対を押し切って、一歩一歩、ゆっくりと街の中を進んだ。
事故が起きた日は身が凍るんじゃないかと危惧するほど寒かったというのに、もう外は青々とした葉が木々を彩っていた。
「きっと、もうすぐ梅雨になるね~。嫌だなぁ」
「……そう、だね」
「もう、もっと楽しもうよ~! ……あ、ねえねえ、ゴールデンウィークはどこに行く?」
「…………」
私は俯いて、自分の手先を見る。自然と両の太ももが視界に入ってきた。右足の質量はスカートの上から全く感じられなくて、見る度に現実を突きつけられる。
思わず視界を外したけれど、今度は目の居場所がなくなった。
しかし、まるで私の思考までも読み取ったかのようなタイミングで、
「モミ、見てみて! 綺麗な花がいっぱい咲いてるよー!!」
スグの弾けるような声に釣られて顔を上げた。目の前に白い花が飛び込んでくる。
「あの花、名前はなんだろうね」
「クチナシ」
疑問を口にするスグに、間髪入れずに答える。すると彼女はコテンと首を傾げ、
「……クチナシ?」
「そう。……あと、さっき通った庭にカーネーションが咲いていたよ。ザクロの木とか、ゼラニウムの鉢もあったかな」
「へえ~」
スグが嬉しそうにニコニコと笑いながら、感嘆の声を上げる。両手を合わせる彼女の表情はイルミネーションの光のように輝いていた。何がスグをそうさせているんだろう。
「やっぱりモミは物知りだな~」
「そんなことないよ。ちょっと記憶力が良いだけ」
「ええー、そう? ……じゃあ、家に帰ったら漢字の練習しようよ。来週小テストがあってさー」
「……ちょっと、それ私が小テスト解けって言うの」
「正解!」
「正解じゃないよ、もう!」
「あははっ」
明るく大きな笑い声に、私も思わず吹き出す。途端に、彼女がこれ以上にないほど顔を綻ばせた。私は目を細めて、
「……スグ」
「何?」
「ありがとね」
一瞬、不意を突かれた時のような間の抜けた顔になった。でも、すぐに歯を見せて笑う。
「こんなのお安い御用だよ!」
キラキラと輝く眩しい笑顔。何も変わらない澄んだ表情。
落下していくだけだった“私”の体に、いつの間にか一本の糸が巻き付いていた。
――――それからは、スグと一緒によく外出をするようになった。もしかしたら、事故の前よりも頻繁に出掛けるようになったかもしれない。
本当に、色々な場所へ連れ回された。動物園や水族館等の定番スポットはもちろんのこと、博覧会やプラネタリウム、ミュージカルからクラシックコンサートまで。果てには絶景を望むことが出来るハイキングコースや公園、何百種類もの花が咲き誇る美しい花園にも連れて行ってもらった。
『色とりどりの景色を見て』と言った彼女は、本当にその言葉通りにしてくれたのだ。
一体どこでそんな場所を見つけてきたんだと、首を傾げてしまうほどの情報量だった。しかも私の体の事を考慮してか、完璧にコースを作り上げて。……自分の時間を切り裂いて、私のために。元々パソコン関係は苦手で、学校の授業以外で触ったことなんてなかったはずなのに、必死にローマ字表と格闘して覚えてしまうまでキーボード入力をしていたことを私は知っている。
……ただ、スグには申し訳ないけれど、以前のように楽しいと純粋に心が躍ることは無くなった。どこへ行っても、どんなに美しいはずの景色を見ても、胸に穴が開いているみたいに感情がすり抜けていく。
それはスグも分かっているようで、必死に私を楽しませようとフォローしてくれた。諦めずに、何度も、何度も私を外の世界へ引っ張ってくれた。
――――そのおかげもあってか、気付いた時には車椅子での移動にはずいぶん慣れていたのだ。一人で十分行動出来るくらいに。
ちなみに、短時間の移動ならばロフストランドクラッチ――――前腕部支持型杖とも呼ばれるもので、前腕を通すカフとグリップで体重を支えるもの――――を右手で使用している。だが、外へ行くにはやはり車椅子を使わなければいけない。杖の支えがあるとはいえ右足で全体重を支えなければいけないので、義足の接続部への負担が大きい。よって、長時間の移動をすることには向いておらず、せいぜい家の中だけだ。
しかし、私をこんな風に行動出来るようにしてくれたのは他でもないスグだろう。
彼女には感謝してもしきれない。
「モミ~、入ってもいい?」
するとそのスグが、声を伸ばしながら軽くドアをノックしてきた。私は浮かべていた笑みを慌てて消し去り、膝の上に乗せていた小ぶりのバッグを机の上へ置く。
「いいわよ」
「はーい」
声と共にドアが開き、中学校の制服を身に付けたスグが顔をのぞかせた。今日は土曜日だが、おそらくいつものように部活へ行くのだろう。
「スグ、どうしたの?」
「ほらっ、今日も出掛けるんでしょ? 途中まで一緒に行かない?」
「いいけれど……、私、もう少し時間が掛かるわよ」
「大丈夫、大丈夫! あたしも手伝うし!」
そう言うが早いか、手慣れた調子で私の外出の準備を始める。こうなってしまったら、もうスグは止められないだろう。素直に手伝ってもらった方が早く終わる。私は苦笑いを作り、肩をすくめた。
「今日もあそこに行くんでしょ?」
「ええ、そうだけれど……、今日はその前に人と会う約束をしていて……」
「人と会う約束?」
スグがバッと私の方を振り返った。目を丸くさせ、驚いたような表情で私の顔を凝視してくる。けれどすぐに、
「……ああ、なるほど。幸歌さんか」
私が補足を入れる隙もなく一人で解決させ、ポンと手を打った。
「そう、幸歌よ」
「会うのは1年ぶりくらいじゃない?」
「そうね……、去年は私も幸歌もバタバタしていたし、4月に入ってからも忙しかったから」
ハンカチとポケットティッシュをバッグに入れながら口にした。
――――今でも思い出せる。
幸歌が事故を聞きつけて病室に駆け込んできたとき、泣きそうな顔をしながらも言ってくれた言葉を。
それは頭にしっかりと焼き付いていて、離れない。
『大丈夫だよ。私がいるから』
頭を優しく撫でながら、私の傍にいてくれた。
私の瞳を、まるで逃すまいとでも言うように、ずっと見ていてくれたのだ。
そんな幸歌は、告げていた通り私の事故の翌年――――学年が変わる頃に引っ越して行った。けれどそれまでは、ほとんど日をおかずにお見舞いに来てくれたのだ。看護師さんに私の家族だと勘違いされてしまうくらいに。
詳しいことは知らないが、幸歌は直前まで引っ越すことを渋ったらしい。私の傍を離れたくないと泣いて、彼女のお姉さんを困らせたそうだ。
結局、幸歌のお姉さんとスグが連絡を取り合い、私と幸歌が文通出来るようにするということで落ち着いた。
それからは、お互い携帯電話を持ちメールが出来るようになっても、少しくらい忙しくても、途絶えさせずに文通が続いている。幸歌からの手紙はそれだけで束を作れるようになり、物がほとんど無い殺風景な私の部屋で、確かな色を放っていた。
「幸歌さんっていい人だよね」
「ええ、そうね」
いつも文頭で、『困っていることはないか、体調を崩していないか』と聞いてくる。優しくて心配性な、掛け替えのない大切な親友だ。
「……まったくモミったら、本当に幸歌さんが好きなんだね」
「もちろんよ。幸歌は私の大事な友人だもの」
「はいはい。……もう、そこまでハッキリ言われると複雑だわ……」
「……は?」
「なんでもありませーん」
ひょいと肩を上げるスグを私は不思議に思いながら、部屋の壁に取り付けられた時計を見上げた。思っていたよりも時間が過ぎていて、慌ててスグの手を止めさせる。
「もう大丈夫よ。これ以上時間を取らせるのは悪いわ。今日も部活があるのでしょう?」
「そんな……、平気だよ」
「駄目よ。時間は守らなくてはいけないわ」
不服そうに唇を尖らせるスグの背中を、手を伸ばしてポンッと軽く叩く。私の動きが制限されていることをスグは十分理解しているから、強く理由を主張して背中を叩けばそれ以上粘ることはしない。
スグは荷物を肩に掛けると、ゆっくりとした足取りで扉に近づいて行った。しかしドアノブに手を乗せたところで私の方へ振り返り、
「ねえモミ、今度友達が入っている吹奏楽部が大会に出るんだけど、日曜日だし3人で応援に行かない?」
「……3人?」
「そう! あたしと、モミと、お兄ちゃんで!」
「――――スグ」
先ほどまでと口調は変わっていない。しかしその声の裏には、どこか願うような力強さがあった。ちょうど七夕に短冊へ願い事を書くみたいに。
私は無意識に目をそらす。
「…………悪いけれど」
「モミ……」
ガッカリしたように、悲しそうに、スグの声音が微かに震える。
「……こ、今回は断らせないんだからね!」
「…………スグ」
「……何でよ、どうして。あたしたち、あんなに仲良かったじゃない!」
「スグ!」
「モミだって、あの日3人で交わした“約束”を覚えてるでしょ!?」
「…………」
スグの必死な表情を見ていられなくて、顔をそらした。唇を噛み締める。
――――覚えてる。
私は、私とスグは覚えている。……けれどそれは、“あの人”も同じように覚えている確証には決してならない。
そもそも、仮に“彼”も覚えていたとしても、あの“約束”がすでに崩れ去っているのは現然たるものだった。
「……色々な理由を付けて3人で行きたがらないよね。小さい頃みたいに、お兄ちゃんとふざけ合うこともないし」
スグは知らない。
――――スグだけが、私たち“兄妹”の真実を知らないのだ。
私は、なんて残酷なことをスグにしているのだろう。あと数年経てば両親から知らされるからと、先延ばしして、隠し通している。
……きっと、怖いのだ。畏怖しているのだ。他でもない、“アイツ”が邪魔をするのだ。いつも、いつも、枯れて潰れた声で叫び続けて、私を不快にさせる “アイツ”が。
「……そんな、もうふざけ合うような歳でもないでしょう?」
「そうだけど……、そうだけど、あたしは……っ」
「スグ。私たちはもう、無邪気な子どもではないのよ。……少なくとも私は、ただ純粋に日々を過ごしていた頃には戻れないわ」
膝の上に乗せていた両手を握りしめた。ロングスカートに皺を作る。
翅を失えば、どんなに美しかった蝶であっても、生気を完全に喪失した醜い死骸に過ぎないのだ。
「……悲しいな。モミがあたしを置いて、先へ行ってしまったみたい」
「私はもう戻れないわ。ならば、先へ進むしかないのよ」
たとえそれが、体の肉を少しずつ切り刻まれていくような激痛に、この命を終えるまで苦しめられる道であったとしても。美しい過去に縋り付くことは、私には許されていないのだ。
愚かな罪人は、てらてらと光る猛毒が塗られた裁縫針の上を、素足で歩むしかない。数えることなど不可能であると言い切っても良いくらい針の先が迎え撃っていたとしても。立ち止まることも、駆け抜けることも、助けを求めることも出来ない。ただただ無慈悲で、冷酷で、孤独なのだ。
「けれどね、スグ。あなたまで急ぐことはないわ」
苦しみもがくのは、歯がガチガチと音を立てるくらい寒い。光を望むなんて滑稽に思えるほどの、果てしなく広がる暗黒の洞窟が続く。歩いても、歩いても、……歩き疲れて息が絶え絶えになっても、出口はおろか行き止まりさえ見つからない。いつ終わるのか、それすら分からない。自分がどこへ向かっているのかも分からない。
そもそもどうしてこの場所に居るのか、その理由を見失いそうになるのだ。
「……モミ、それってどういう……?」
「分からなくて良いわ。けれど、これだけは覚えていてちょうだい」
眉間に皺を寄せて、口をぎゅっと引き締めるスグへゆっくり近づいていく。腕を伸ばして、彼女の肩に手を置いた。
……あなたには、太陽の光がさんさんと降り注ぐ場所で生きて行ってほしい。
そう願うことだけが、私に出来る最善のことだった。
「――――来なくても良い場所だってあるのよ」
スグの表情が一層険しいものへと変わっていく。
「来なくても……、良い場所?」
「考えなくてもいいわ。ただ、覚えているだけでいいのよ」
「何それ。意味が分からないよ」
「……自分が幸せになれると思った道を、ちゃんと選び取るだけで良いの」
いつか、私が取り返しのつかないことになったとしても。スグまで追いかけて来なくても良いのだ。
スグは優しい。……けれど、それだけ危うさもあるのだ。
「……や、やだ。何なの、まるで遺言みたいじゃない!」
肩に置いていた手が、バッと振り払われた。すぐさま視線を戻すと、スグがわなわなと体を震わせ、ギッと目尻を吊り上げている。
「それに、その“来なくても良い場所”にモミがいるってことじゃないの!?」
顔を真っ赤にして激昂する彼女を、“私”は静かに見つめる。何も言わず、視線も動かさず、表情も変えず。するとそんな私に痺れを切らしたのか、スグが飛び掛かかってくるような勢いで私の両肩を掴んだ。力加減が出来ないほど感情が高ぶっているのか、爪が肉に食い込む。
しかし、“私”はそれでも、何の感情も動かさない。スグの整った顔が歪んだ。
「何がモミを苦しめているの!? 何がそうさせているの!? ……やっぱりあたし、分かんないよっ! ちゃんと教えてよ!!」
ハラリと舞った雫が、私の頬を濡らした。苦痛に満ちた、絞り出すような声が落ちてくる。
「3人で笑っていたあの頃に、戻りたいよ……っ!!」
肩を掴む両手が、フルフルと細かく震えていた。私は短くため息を吐き出すと、そっとその手を降ろさせる。
「――――スグ」
俯き加減だったショートヘアの少女が、ビクリと体を跳ねさせた。恐る恐るといった風に、顔が上げられる。
「スグ」
赤くさせた両目が、私の両目とぶつかった。瞬間、悔しそうな、何かを察して諦めたような、それでいて縋るような――――、そんな感情が複雑に入り混じった面持ちになる。
私は息を吸うと、目を細めて冷たく言い放った。
「スグ、学校へ行きなさい。もう予定時刻をとっくに過ぎているはずよ」
「モミ、あたしは……」
「行きなさい。私は、やるべき事を全うしない人間とは話したくないわ」
「……うん、分かった。ごめんなさい」
さっと顔ごと視線が外された。一言も発さないまま、背を向けて部屋から出て行く。
バタン。その乾いた音が、この空間を淡い光から完全に切り離した。途端、重い空気が体に圧し掛かってくる。
――――私は、先へ進まなければいけないのだ。
大多数の人間と大きく考えが違っていようが、私には関係ない。奇妙に見られても、疎まれても、嘲笑されても、私は別に構わない。何とでも言えば良いのだ。
机の隅に置かれた黒いノートパソコンを見やる。自由に動けなくなった私のために、両親が買い与えてくれたものだ。元々インターネットにはあまり興味が無かったが、せっかく気を使ってくれたのだからと、私はネットで色々な情報を見るようになった。
そうしてしばらくたった頃、あるゲームの名前を再び目にしたのだ。
剣の世界――――≪ソードアート・オンライン≫。
それは、私がモンスターのデザイン案を提供したゲームだった。
ゲームなどには一切見向きもしない私だが、この時は違った。忌々しい出来事も思い出すことになったが、どんな作品に自分のイラストが使われたのか気になり、ゲームの紹介をしていたブログのリンクから公式ホームページへ飛んだ。
そして私は、衝撃を受けた。
この世界の中で、生活出来るということに。
――――“生きる”ことが出来るということに。
生物学上、私は生きている。けれどもう、私にとってこの体は死んだも同然だったのだ。
川に落ちた一枚の葉のように漂い、いつか朽ちるのを待つ存在。
私の事を支えようとしてくれた人はもちろんいた。しかし、存在しても良い場所も、自身の価値も見出せなかった。
……けれど、この世界に行けたらどうなのだろう。
モンスターを狩って生活し、家を持ち、釣りをし、畑を耕す――――。そんな日々を過ごすことが出来る。
ある程度のルールはあるが、それはこちらだって行動を制限するものはいくらでもある。それを考えれば、この世界は遥かに自由なのだ。
ならば、自分の価値を自分で作り上げることが出来るのではないか。
自分の脚で歩いて、走って、跳ねることが出来るだから。何物にも、私は縛られないのだから。
――――もし、この世界を“もう一つの現実世界”に出来るなら。
時間だけが浪費するように進むなかで、置いて行かれた私が先へ進めるなら。
私は、もう一度生きることが出来る。この世界で死んだのなら、そちらの世界の住人になればいい。それで私が生きることが出来るのなら、……たとえニセモノだらけの世界だとしても構わない。
ただ、これの意味することはすなわち、今の世界で“生きる”ことをやめるということなのだ。しかしすでに私自身が、今生かされている世界を拒絶している。
もちろん、スグや幸歌、伸一の顔が浮かばなかったわけではない。だが、迷うことはなかった。
たとえ“もう一つの現実世界”から“己の生きる世界”と認識が変わり、破滅への一途をたどったとしても、後悔はしないだろう。
そもそも、すでに私は毒針の道を進んでいるのだ。多種多彩な花が咲き、光り輝いている道はもう踏み外しているのだ。
今以上の暗闇に突き進んだとして、何が変わるのだろうか?
≪ソードアート・オンライン≫の予約は無事に済んでいる。あとは数日後に届くのを待つだけであった。
心躍る、なんていうことは特にない。ただその日を待つだけだ。
小ぶりのバックを膝の上へ乗せ、車椅子の車輪の外側に付いたハンドリムを操作する。私の部屋は1階へ移動させてもらったので、部屋の外に出れば玄関は目と鼻の先だ。
――――なんだけれども。
私の動きは、自然と止まった。
「……あ、紅葉」
玄関の方向から歩いてきた人物もこちらに気づき、私の名前を呼んで足を止めた。
……そう、玄関に近いということは、それだけ“彼”と鉢合わせをする確率が上がるし、引き返すことも出来ない。
私はろこつに嫌な顔をして、わざと見せつける。
「2人の時にその呼び方はやめてって言っているでしょう?」
何か言葉が返ってくる前に、ドスを利かせて刺々しく言ってやった。
「――――和人さん」

「……ごめん、紅葉さん」
もともと逸らされていた視線が、さらに落ち込む。私は口に馬鹿にするような笑みを作り上げると、ハンドリムを操作して和人の方へ近づく。彼の肩が、少しだけ揺れた。
「恐れ入りますが、そこを通して頂けませんか?」
「あ、ああ、ごめん。……ごめんなさい。あの、手伝おうか?」
「いいえ、結構です。慣れていますので」
彼の体が脇へ逸れたのを確認して、車椅子の操作を再開した。だが和人とすれ違った瞬間、声が掛けられる。
「いつものとこに行くのか?」
「あなたには関係のないことだわ。……いつも言っているでしょう。私に関わらないでいいですから」
私は嫌悪に顔を潜めながら、冷たい声で素っ気なく言い放つ。
痛いほどの静寂が包んだ。
この空気を作っているのは私だと、十分理解している。けれど破ろうとは思わない。
背後にいる和人の様子はもうわからない。……といっても、彼はいつものように目を逸らして、顔を俯けているだろうから、分かるはずもないのだが。
怒りか、悲しみか、はたまたそれ以外の感情か。
私には、もう確認する術はない。
だがどんな感情を抱いているとしても、もう関係ないのだ。
私は追い打ちをかけるべく、必ず傷つくと分かっている言葉を投下する。どんな事よりも、苦しいものと知っているから。
「本当の兄じゃないくせに」
これ以上の会話は時間の“無駄”だ。
さらに反応が返ってくる前に手早くハンドリムを操作した。玄関付近で車椅子の車輪に付けたカバーを外す。そして感情が出ないように玄関のドアを開け、そっと、けれど後ろは振りかえずに閉めた。
私の後を追いかけてくるものは、当然のことながら誰一人としていなかった。
――――しかし、門を出たところで待ち構えている者はいた。
「あら……、伸一じゃない」
全く予想していなかった人物に、私は目を丸くする。それは向こうも同じだったようで、人の家の前で何やら難しい顔をしていたくせに、ビクリと小動物のように跳ね上がる。
「も、紅葉ちゃん」
「そんな、まるで幽霊でも見たみたいな反応をしないでちょうだい」
「ご、ごめん」
しゅんと肩を落とす彼に、私は表情を柔らかくした。尖っていた感情が、雪解けのように穏やかになっていく。
「まあ、いいわ。……それで、ウチに何の用かしら。あいにくだけど、スグは部活に行ったわよ」
「そ……っ、そんなんじゃないよ!!」
顔を真っ赤にさせて間髪入れずに言い返してくる伸一に、私は苦笑いを作った。
「あなた、まだスグと話せていないのね」
「う、うぐっ……」
声を詰まらせたかと思うと、彼は明後日の方向を見て、
「……いいんだよ、見ているだけで」
「同じようなことを、もう何年も言っているわよ?」
「うう……」
ついからかってやると、拗ねたように口を尖らせる。彼は気づいていないが、私や幸歌以外にはこんな表情はしない。微笑ましくなり、私は笑みを浮かべる。
「伸一のことを信頼しているから言うけれど、出来るならあなたにスグを守ってほしいわ」
「へ? どうして」
「スグは、私にとって大切な人のうちの一人よ。そう思うのは当然だわ」
「そ、そうじゃなくて。……どうして僕なの?」
本当に分からないようで、伸一が間の抜けた顔で私の目を見詰め返してくる。私は小さく息を吸った。
「……私が今心から信頼しているのは、幸歌と、スグと、……伸一だけだもの」
「ええっ!?」
「どうして驚くのかしら。当たり前じゃない」
伸一が唖然とした表情で、口をパクパクと開閉させている。思わずクスクスと笑うと、彼はフリーズから立ち直ったのか、頬を赤くさせたまま頭をガシガシと掻き、
「紅葉ちゃんってさ、よくそういう恥ずかしいこと言うよね……」
「どうして恥ずかしいのよ。本当のことじゃない。嘘は言っていないわ」
「分かってるよ! ……だから、余計恥ずかし――――ああ、もういいや」
「何よ、はっきりしないわね」
口元を手で押さえてそっぽを向く伸一に呆れ、眉をひそめる。だが、同時に違う可能性が頭の中に浮かんだ。
「それとも、あなたにとって私のこの気持ちは重いのかしら」
刹那、伸一が顔を上げる。ギョッとしたような顔だった。彼は私が口を挟む間もなく早口で、
「そんなことない! 嬉しいよ。……僕も、紅葉ちゃんは大切な友達だって思ってるんだから!」
「……そう。ありがとう、私も嬉しいわ」
――――人間とは残酷で、嘘をつく生き物だ。どんなに正しさを貫く人物でも、自己中心的になる時はある。聖人のような人などごく一部だ。すなわち、『清く正しく、どんな人に対しても差別せずに優しく』などほぼ不可能だと言ってもいい。
しかしそれでも、目の前にいる彼は、少なくとも私にとっては“優しい人”だ。
確かに教室に通っていた頃と比べれば、伸一とは少し疎遠になっただろう。けれどもこうして会えば対等に接してくれるし、私も躊躇いなくそう出来る。
“普通”に話してくれる数少ない友人だ。
「……そうだ、伸一。これから幸歌と会う約束をしているのだけれど、あなたも来る? きっと幸歌も喜ぶわ」
「う、うーん……」
「この後何か予定でもあるのかしら」
「そ、そういうわけじゃないんだけど……」
「それだったらいいじゃない。もう少し伸一と話したいわ」
思案する表情になる伸一を見詰める。彼は目を泳がせたが、やがてコクンと一つ頷いた。
「じゃ、じゃあ……」
「決まりね。さ、行きましょ?」
伸一が私の横に並んだのを確認して、ハンドリムを操作し始める。はじめ彼は歩幅を小さくし歩行スピードを緩めようとしてくれたみたいだが、車椅子の操作に慣れた今となっては一般的な人が歩く速度とそう変わらない。彼の優しさに感謝しつつ、私たちは進む。
「そういえば、伸一。この前駅でバレエ教室の先生にお会いしたのだけれど、あなた教室をやめたんですってね」
「……うん、やめたよ」
「……どうして、と問い詰めたりしないわ。何をしようが伸一の勝手だもの。けれど」
「そんな深い理由はないよ。ただ……」
「ただ?」
一瞬黙り込む彼だったが、意を決したように口を再び開く。
「僕さ、たとえクラスがバラバラになってしまっても、3人で夜の帰り道を歩けるのが楽しかったんだ」
「……そうね。“私”も楽しかったわ」
「うん。――――紅葉ちゃんがバレエの楽しさを教えてくれた。……幸歌ちゃんが、躍ることの嬉しさを教えてくれた」
あの頃の時間は、色鮮やかだった。
私もそれを思い出して、軽く目を閉じる。
「紅葉ちゃんはいつも凄く厳しくて怖かったけれど、紅葉ちゃんがバレエを大好きなのはよく知っていたから、僕も精一杯頑張った。……たとえ上手く出来なくても、頑張ること自体が凄く楽しかったんだ」
伸一が立ち止まった。見上げれば彼の目はユラユラと切なげに揺れていて、私は何も言えなくなる。
「けれど幸歌ちゃんは引っ越して行ってしまって、紅葉ちゃんは……バレエが出来なくなってしまって、僕があの教室にいる意味はなんだろうって思って」
「それで……、やめてしまったの?」
「……うん、そうだよ」
……これはきっと、彼の優しさ。弱さ。
細い息が自身の口から漏れ出る。眉を八の字にしながら言葉を探し……、しかしどう言えばいいのか分からなった。
私は押し黙ったまま、ハンドリムの操作を再開した。知らず知らずのうちに、ポツリと言葉が漏れ出る。
「馬鹿ね」
それを聞いた伸一も泣きそうな表情で苦笑いを浮かべ、
「ごめん」
震えた声だった。深い、深い、暗い底を覗き込んだような、悲しみを孕んだ声音だった。
「本当、馬鹿だわ……」
「うん。知ってる」
「もう……」
私は瞑目し、――――しかしすぐに目を開けた。
「でもね、私、あなたのそういう所も嫌いじゃないわ」
伸一が両目を見開く。私は何も言わずに笑みを作り、彼から目を外して前を見据えた。
*
駅から一番近い大きめの公園。時刻は14時をちょうど刻んだ頃だ。
滑り台や鉄棒の周りでは小学校低学年の子どもたちが笑い声を上げながら走り回り、広い砂地では親子がキャッチボールをしている。
賑やかで穏やかな空間だ。私は口元を緩ませる。
視線を巡らせれば、大きな木の下に設置されたベンチに人影があった。読書中で顔は俯けられていたが、雰囲気は全く変わらない。今日会う約束をしている幸歌だ。ピンク色のワンピースを着ている。
私は伸一と顔を見合わせると、ゆっくり近づいて声を掛ける。
「久しぶり、幸歌」
少女の顔が上がる。ふわりと髪が風に舞った。
「あ、久しぶり紅葉――――って」
私の顔を見て笑った幸歌だったが、背後に立つ伸一を見て動きを止めた。ボンッと小さい爆発が幸歌の顔で起きる。顔をゆでダコのように真っ赤にさせ、ガバッと勢いよく立ち上がった。
「な、なななななな、何で長田君が……っ」
「あら、駄目だったかしら。来る途中で会ったから、せっかくなら3人で、って思ったのだけれど」
「ううん、別に駄目じゃなくて……、むしろ……う、うれし……」
「幸歌?」
「何でもない!」
ブンブンと顔を横に振ったかと思うと、両手で顔を覆ってトスンと再びベンチに沈んだ。本当に幸歌は可愛い。
一方、その様子を伸一はきょとんとした表情で見ていて、何も分かっていないご様子だ。さすがに呆れてくる。私は眉を吊り上げながら、肘で彼の脇腹を小突いた。
「なっ、何、紅葉ちゃん」
「別に何でもないわ」
私は大きなため息をつき、幸歌の細い肩に手を置いた。
「幸歌、驚かせてごめんなさい」
「ううん、ありがと……」
手を退けた彼女は、ふにゃりと笑う。桃色に染まった頬が愛らしい。
あいかわらず彼女の笑顔は朗らかで優しかった。柔らかな声が、耳によく馴染む。
彼女も今までと変わらない視線を向けてくれる一人だと、そう素直に思える。
「ごめんね。大変だったでしょ」
「いいえ、大丈夫よ。そもそも、今日も外へ出るつもりだったから」
「そう? ……あ、長田君も、ええと、ありがと」
「い、いや……」
チラリと視線を向けられた伸一が、ぎこちなく言葉を返す。幸歌もあちこち目をやり落ち着かない様子だ。だが、ベンチの横に置かれた紙袋を見た時、「あっ」と短く声を上げる。
「そうそう! 今のうちに渡しておかなきゃ」
きっとどこかの雑貨屋でラッピング用のものを購入してきたのだろう。パステルブルーのチェック柄が可愛らしく、幸歌らしい。
彼女は高らかに手を打つと、宝物を手にするかのような手つきでその紙袋のヒモを掴む。そして私に向かって差し出し、
「はいこれ、お祝い!」
いきなりのことで私は面食らった。咄嗟に言葉が思いつかない。
「……え、お祝いって、まさか」
「そうそう、そのまさかだよ。直接渡したかったから、半年以上遅れちゃったけどね~」
「……合格? ……って、何? 紅葉ちゃん、何か資格でも取ったの?」
すると、ただ一人状況を飲み込めていない伸一が首を傾げて問うてくる。幸歌は目を丸くすると、私の顔を凝視して、
「紅葉、長田君に話してないの!?」
「ええ。……だって、わざわざ言うようなことでもないでしょう?」
「そういう問題じゃないよ~……」
呆れたような声を出すと、ガックリと幸歌が肩を落として脱力した。私はどうしてそんな反応をされるのかよく分からず首を傾げる。
「な、何なんだよ。早く説明してよ」
我慢の限界になったのか、伸一が急かした。幸歌にチラリと目配せすると、彼女は諦めたように苦笑いをし、
「ほら、3年くらい前に外国の教育方法を取り入れるってことになって、飛び級制度が日本にも出来たでしょ」
「……あ、ああ、そういえばそんな制度が出来たような――――って、それって!?」
「そういうこと!」
幸歌はまるで自分の事を自慢するかのように胸を張り、
「紅葉は小4の秋に一回目の試験を受けて、ええと、……何年生に進級したんだっけ」
「中学2年生よ」
「そうそう、中2!」
さらっと補足をすれば、幸歌は笑顔で両手を打った。
「……あ、だから紅葉ちゃん転校しちゃったのか……」
3年の時を経て知った真実に、伸一が遠い目をして深く息を吐き出す。それを見た幸歌が一瞬つらそうな表情をしたが、すぐに消し去り、
「それで去年二回目の試験を受けて、また合格したんだよね。国立大学の1年生だっけ」
「ええ。理学部物理学科に入学したわ」
「ひ、ひえー……」
「もうさ、私より3つも学年が上だなんてヒドイよね~」
「そんなこと言われても……。今打ち込めるものと言ったら、勉強くらいなんだもの」
「だからって、そんなに頑張らないでよ~」
幸歌は、ぷぅと頬を膨らませながらそう言った。そんな彼女を見て、一瞬、私は思う。
――――優秀な成績を残したら自分の価値を見出せるのではないかと考えていた、と言ったらどんな表情をするのだろうと。
そしてもっとも大きな理由として、勉学は“私”が一番嫌いなことだったから一生懸命やっている、なんて教えたら……と。
けれど、その考えはすぐにそれは打ち消した。判断時間にして、ほんの数秒。その速さのおかげか、幸歌と伸一が気づいた様子はない。
私はほっとしながらも、表は崩さないように笑顔を作った。
「あ、そうだ、二人に相談したいことがあってね……。見てほしいものがあるのんだ」
幸歌は言うやいなや肩掛けのバックを探り始めた。彼女はおっとりとした性格の女の子だが、同時におしゃべり好きの面もある。私から話題を振ることはあまりないが、話題が絶えることはない。
私は笑みを作りながら見守っていると、やがて幸歌は目的のものは見つけたようで、パッと顔が明るくなった。再びこちらを見てにっこりと笑う。
うすいピンクの花が舞っているメモ紙を手渡された。そこには、何かのグループの名前なのか、数個箇条書きで書かれていた。
「……ええと、幸歌? 何かしら、これ」
「うん。実は私、高校でパソコン部に入っているんだけど……」
「パソコン部? 幸歌が?」
思わず聞き返した。途端、幸歌が「しまった」とでも言うような表情になる。
「あ、えっと、友達のお兄さんに誘われて……」
「……私、てっきり声楽部とか合唱部に入ったものだと思っていたのだけれど」
あの夜の約束を思い出す。
必ずそれぞれの夢を叶えよう、と誓い合ったあの日を。
私はそのすぐ後に不可能な未来へと変わってしまったが、幸歌は叶えるチャンスがあるはずなのに。
「幸歌、部活だって重要なアピール場所よ。それなのに……」
「そ、それは……」
幸歌が今日初めて目をそらした。同じだ、と咄嗟にその言葉が頭に浮かぶ。
何と、と考えるまでもない。引っ越す事を告げたあの時の表情とそっくりなのだ。
嫌な予感がした。ピリピリとした感覚が電流のように走る。私はすぐさま問おうとしたが、それとほぼ同時に、
「――――あ、あの、紅葉ちゃん!」
伸一が大声を上げて割り込んできた。幸歌が目を真ん丸にさせる。私も突然のことに驚き、言葉を失った。けれどもすぐに気を取り直し、
「伸一、何かしら。今大切な話をしているのよ」
「だ、だけど」
「それともあなた、何か知っているのかしら」
「……な、何も知らないよ」
「そう?」
スッと目を細める。伸一は身を固くさせ、幸歌はオロオロとした様子で私たちの顔を交互に見ていた。誰一人として何も言わない。
子供たちの笑い声が、急に大きく聞こえだした。ザアザアと、葉の泣く音が私たちの間を流れていく。
私は深くため息をついて、知らず知らずのうちに入っていた体の力を抜いた。
……何をしているのだろう、私は。
幸歌がどんな部活を選ぼうが、彼女の自由だ。どんな将来を夢見て、どんな道を選ぼうが自由だ。
人は変わる。……変わらない人などいない。
当たり前のことだ。
幸歌も、伸一も、みんな変わっていく。私自身が良い例ではないか。
歌を歌っていてほしいなど、己の願望だ。それを押し付けるなんてどうかしている。
「……ごめんなさい、幸歌」
「え?」
「伸一にも謝らなければいけないわね。……ごめんなさい」
二人に頭を下げた。伸ばした黒髪が肩からさらさらとこぼれ、私の視界に影を落とす。
「ちょっ、ちょっと、紅葉ちゃん! 謝らないでよ!」
「そうだよ! 私、全然気にしてないから!」
「いいえ、そういうわけには……」
「大丈夫だから、本当に!」
「え、ええと、――――ほら、幸歌ちゃん、相談事って何?」
「……あっ、うん!」
伸一が無理やり話の路線を変えた。幸歌がワタワタとしながらも話し出す。
「じ、実はね、部活の人たちでオンラインゲームをすることになったんだけど……」
「うんうん」
伸一が相槌を打つのを聞いて、そっと顔を上げた。すると、二人はホッとしたような色を顔に浮かべる。
「……それでね、すぐには作れないらしいんだけど、ギルドっていうやつを作ろうと思っているの。これが名前の候補なんだけれど、なかなか決まらなくて」
「あー、ギルドか。確かに名前決めは悩むかもね」
己の手の中にある紙に視線を落とす。
ギルド――――事前にゲームについて調べた時に出てきたワードだ。確かチームのようなものであった気がする。……とすると、たしかにこれらの案は少し微妙かもしれない。高校名が入っていたり、個人の名前らしきものが入っていたり……、これは駄目でしょうと、つっこみたくなるものまである。
しかし、少々呆れながら視線を下に滑らせていくと、目に留まったものがあった。思わずそれを凝視し、気づいた時には声も出ていた。
「≪月夜の黒猫団≫…?」
何か惹かれるものが、この名前のそこかしこにあった。
そろそろと紙からゆっくり顔を上げる。瞬間、幸歌の表情を見て確信した。けれど、確かめる言葉が口から滑り出る。
「もしかして……、あの時の猫のこと?」
「あ、やっぱり分かった?」
「ええ。少し驚いたけれど。……ねえ、リュヌは元気かしら」
「元気すぎて困っているくらいだよ」
あはは、と幸歌は笑う。けれどもすぐに神妙な面持ちになり、少し眉を下げながら心配そうに言葉を発した。
「……ごめん、嫌だった?」
事故に合った日と同じ日だから、と続けなくともそう言いたいのが分かった。だから私は、否定の意をこめて静かに首を横に振る。
「いいえ。……むしろ、嬉しいわ。思い出を大切にしてくれているって分かるもの」
「そ……、そう?」
「ええ、もちろん。……じゃあ私、≪月夜の黒猫団≫に1票を入れるわ。可愛い名前だと思うから」
「ほ、本当!? よかった!」
再び幸歌の周りにコスモスの花が舞う。それは優しい色の花びらで、まぶしさに目が眩みそうになる。けれど私は視線をそらさず微笑みを作りながらその姿を見て、静かに聞いた。
「ところで、そのゲームの名前は何なのかしら」
「≪ソードアート・オンライン≫っていうゲームだよ。今結構テレビとかで騒いでいるやつ!」
「ああ、知っているわ。……それにしても、偶然ね。実は私もやろうと思っているのよ」
「そうなの? 紅葉がゲームだなんて珍しいね。……あ、自分のデザインしたモンスターが気になるとか?」
純粋な質問に、一瞬言葉が詰まった。
“珍しい”。
確かにそうだ。私自身でさえ少し前の己を思えば、そんな道楽に身を投じるなんて奇妙に感じてしまうのだから。……けれど、 “もう一つの世界にしたい”、なんて口が裂けても幸歌には言えない。
ただ純粋に“ゲーム”を楽しもうとしている、彼女には。
……真っ白で美しい輝きを放つ彼らを、醜い色で染めてはならないのだ。
私はぐっと体に力を込める。口にすることは許されないと叫ぶ理性が、ギリギリと“自身”の身を縛り上げた。
ギリギリ、ギリギリ。
かつて“私”を落下から助けた3本の糸が、自重で食い込む。タラリと、どす黒く熱い液体がこぼれた。あちこちから止めどなく溢れ出る液体と混じる。
ボタボタ、ボタボタ。
ぐらぐら、ぐらぐら。
上も下も右も左も見えない暗闇。熱さが肌を少しずつ焦がし、寒さが体を鋭く突き刺す場所。そこで宙ぶらりんの状態になっている“私”。
口元を綻ばせた。愛しい姉や友人の顔を思い浮かべながら、糸を自らの手で断ち切る。
「――――ええ、そんなところよ」
落ちる、落ちていく。
……いや、一滴の白すら垂らされていないような黒の中では、その感覚でさえ失われていた。
落ちているのか、底まで来たのか、それともすでに底に居たのか。
もう、分からない。
己の手すら視えない。
そして、誰も“私”が居る場所を知らない。
「……伸一は?」
「へ?」
ゆらゆらと揺れる思考を押しとどめ、数秒の間を置いた後、伸一の方へ顔を向けて尋ねた。間抜けな声が上がる。私はその反応に苦笑いをし、
「だから、あなたは≪ソードアート・オンライン≫をやらないの?」
「あっ、それは……」
何気なく聞いたつもりだったのだが、何故かチラリと幸歌へ視線を送る。彼女も伸一のそれを受け、気まずそうに俯いた。
その意味ありげな視線での会話を、不思議に思って首を傾げる。
「どうしたの? 何かおかしな事でも言ったかしら」
「う、ううん。そういうわけじゃないよ」
「そう?」
「うん。……それで≪ソードアート・オンライン≫だけど、僕は落ち着いてから始めようかなって。買うのが大変そうだから」
「あら、珍しいじゃない。あなたがこんな話題になっている新作に飛びつかないなんて」
「親が勉強しろって五月蠅くてさ」
「……なるほど」
それならまあ、納得出来る。スグも中学に上がってから苦手な教科では苦戦しているようで、何度勉強を教えたことか。
「二人はプレイヤーネームもう決めたの?」
「ええ、決めてあるわ」
「うん、私も!」
「幸歌は≪サチ≫、かしら?」
「……え! 正解! なんでわかったの!?」
「ふふ、何でかしら?」
「もう! そういう紅葉は何にするの?」
「“Kika”って書いて、≪キカ≫にするつもりよ」
「キカ?」
伸一と幸歌が同時に声を上げた。
「……え、どうして≪キカ≫なの?」
「“Momizi”に“K”なんて入ってないし……」
「ふふふ、秘密よ。……でも、一つ目の理由はすぐ分かると思うけれど」
もう一つの現実世界での名前――――、それは変えることが出来ないらしいし、ずっと使っていく大切な名前だ。だから、私はそれに“Kika”を選んだ。
理由は2つ。
一つ目の理由は、私にとっては掛け替えのない、輝いている思い出の象徴から取った。それはとても大切で、絶対に失いたくないものだ。だからこそ、“もう一つの現実世界”にもその欠片だけでも持っていこうと思ったのだ。
そして二つ目は、私自身が己に科した戒め。この名を呼ばれるたびに痛みを感じて、決して許されない罪を思い知るために。
……とまぁ、二つ目はともかく、幸歌ならきっと一つ目にはすぐに気が付くはずだ。と思っていたのだけれど。
「ええ!? うそ……何? 何かの単語? フランス語とか?」
「さぁ、どうでしょう」
本当に分からないらしく、うんうんと頭を押さえて唸りだした。その姿に心が和む。
続いて伸一の方を見ると、手を顎に当てて考え込んでいた。もしかしたら彼は気づくかもしれない。
「うーん、じゃあ、ゆっくり考えてもらおうかしら。……ちなみに、理由は2つあるわよ」
「もう、いじわるだなぁ。……いいよ、後で辞書使うから」
「頑張ってください」
澄まして言えば、幸歌がむうと頬を膨らませた。まるでハムスターか何かのようだと思いながら見ていると、彼女がぷっと吹き出して笑い出す。伸一もそれに釣られたのか、笑顔を浮かべた。
「あ、ねえねえ、紅葉! ……ううん、キカ! 私たちのギルドに入らない!?」
「ギルドって、……さっき話していた≪月夜の黒猫団≫?」
「そう! みんないい人たちだよ! きっと仲良くなれる。私からみんなにお願いするからさ。……ね、どうかな?」
そう笑顔で誘ってくる彼女を、どこか遠い気持ちで眺めた。
――――幸歌と同じギルド。
それはとても魅力的に感じられた。きっと、幸歌やその友人と共にとても素晴らしい時間を過ごすことが出来るだろうと確信できたからだ。
私は俯き、唇を噛み締めた。
「……とても嬉しい話だけれど……、ごめんなさい。遠慮させてもらうわ」
先ほど再認識したばかりなのだ。私と彼女たちの目的は明らかに違う。どう解釈したとしても幸歌たちのまっすぐな線とは交わることはない。
スタート地点から違うもの同士が真っ向からぶつかれば、どうなるかは目に見えていた。人間関係なんて、少しのすれ違いで、ほんの小さなヒビで、粉々になって跡形もなくなってしまう。どんなに仲がよくても、所詮硝子細工のように脆いのだ。
どちらも“リアル”での友人。優しい幸歌なら選び取ることが出来ず、板挟みになってしまうだろう。
そもそも、私がいつかギルドに入る時がきたとしたら、間違いなく “現実世界”で全く交流の無い人にする。……むしろ、そうでなくてはならない。“桐ケ谷紅葉”を知る人物が、一人でも居てはならないのだ。
「ごめんなさい、幸歌」
再度軽く頭を下げて謝る。ぼうっとしていた様子だった彼女は、慌てた様子で顔の前で両手を振り、
「だ、大丈夫だよ! 私もいきなり過ぎたかなって思っているし、気にしないで!」
「そうそう、そういう事はゲームの中でも相談出来るだろうし! 今はとりあえず、保留ってことにしておけば? ≪SAO≫にログインしたら気が変わるかもしれないし」
「……ええ、そうね」
私の思考は露知らず、二人はまた笑って「気にしないで」と言う。
申し訳なさが、胸を締め付けた。
「――――そういえば、紅葉、時間は大丈夫なの? どこか行くって手紙に書いてなかったっけ」
「……あ、ああ、もうそんな時間になってしまったのね」
幸歌に聞かれて時刻を確かめれば、確かにもうそろそろ移動しなければいけない時間だった。子どもの人数が、先ほど見た時よりも増えている。
元々そんな長い時間会う約束では無かった。幸歌がこちらに寄ると言うので、電話で急遽交わした約束だったのだ。……ただそれが分かっていても、名残惜しい雰囲気はもちろんあった。幸歌も何か察した様子の伸一も、浮かない顔をしたので、私は思わず、
「良かったら二人も来る? ここからすぐ近くにあるから」
「……え、でも大丈夫なの?」
「そもそも紅葉はどこに行くの? 手紙でも電話でも、何も言ってなかったよね」
「児童養護施設よ。小学生に勉強を教えるボランティアをしているの。……本当は私の年齢では出来ないのだけれど、施設長の方が母の知り合いらしくてね。掛け合ってくれたらしいわ」
「……そういう施設ってさ、僕みたいな無関係の人間が行くのは難しいんじゃない?」
伸一が渋るような顔つきになった。幸歌も眉を寄せて、困ったような顔になる。
「そうね。……なら、私が今から電話してみるわ」
「う、うん」
やはり私も、少しでも長く二人と一緒にいたいという心理が働いているようだ。素早くハンドリムを操作しベンチから離れると、スマートフォンを鞄の中から取り出す。迷うことなく施設の電話番号へコールした。程なくして電話が繋がる。
『はい、弥栄学園でございます』
「私、学習ボランティアに参加している桐ケ谷紅葉と申します」
『ああ、紅葉ちゃんね。どうしたの?』
「実は――――」
手短に幸歌と伸一の事を話す。彼らがいかに真面目で、優しい性格であるかということも。
「どうだった?」
数分の通話を終え二人の元へ戻ると、すぐさま緊張気味な表情で声を掛けられた。私は笑みを作り、
「明日、11月生まれの子たちのお誕生日会があるそうなの。だから、その買い出しと準備のお手伝いをしてください、だそうよ」
「じゃあ、もう少し紅葉と居られるんだね!」
幸歌が満面の笑みを浮かべる。伸一もどことなく嬉しそうな顔だ。
「よし、紅葉行こう! 早く!」
「もう、そんなに急がなくてもいいでしょう?」
「え~」
「じゃあ僕、紅葉ちゃんの車椅子押そうかな」
「伸一までそんな事言って……。大丈夫よ、一人で出来るわ」
「遠慮しないでよ」
「遠慮なんかしていないわ。伸一にやられると怪我しそうで怖いから言っているのよ」
「ひ、ひどっ」
「あははっ、紅葉~、照れてるの?」
「照れる? 私が? どうして伸一相手に照れなければいけないのかしら」
「……紅葉ちゃん、僕もうそろそろ泣きそうだよ」
ボソリと伸一が呟くと、耐えかねたように幸歌が吹き出した。彼女は目元に浮かんだ涙をぬぐい、
「ね、今度さ、3人でどこか行かない?」
「あ、いいね!」
ゆっくり、ゆっくり私たちは進む。何だかんだ言いつつも、私は伸一に車椅子を任せていた。
「じゃあさ、水族館はどう?」
「……そういえば、来月リニューアルオープンする所があるって聞いたけれど」
「そうそう、そこ!」
「へえ~、いいねぇ! 私、水族館は久しぶりかも」
「あ、そうなの? じゃあ、冬休みにみんなで行こう!」
伸一が車椅子を押す手を止めた。その代りに、右手の小指を私たちに向かって出してくる。すぐに彼の意図を汲んだ幸歌が、その指に自身の指を絡ませた。
「ほら、紅葉も!」
「……まったく、この歳にもなってゆびきり?」
呆れた言葉を返しつつも、私も指を絡めた。
「「「約束」」」
今度こそは、絶対に。
何故かそんな言葉が頭の中に生じた。
*
木々に囲まれた児童養護施設。
カラフルな鉄棒や滑り台を横目に通り過ぎ、正面玄関の裏にある職員用の玄関から中へ入る。
「お姉ちゃん! 紅葉お姉ちゃん!」
「みんなーっ、お姉ちゃんが来たよ!」
今か今かと待ち構えていた様子だった女の子二人が声を張り上げる。バタバタといくつもの足音が楽しげな笑い声と共に近づいてきて、瞬く間に周りを囲まれた。
「みんな、走ってはいけないわよ。危ないわ」
「大丈夫だよ!」
突進してきた子どもたちにそう注意すると、小学4年生の男の子が歯を見せて笑った。私も「仕方がないな」と思いつつも、笑みを浮かべる。
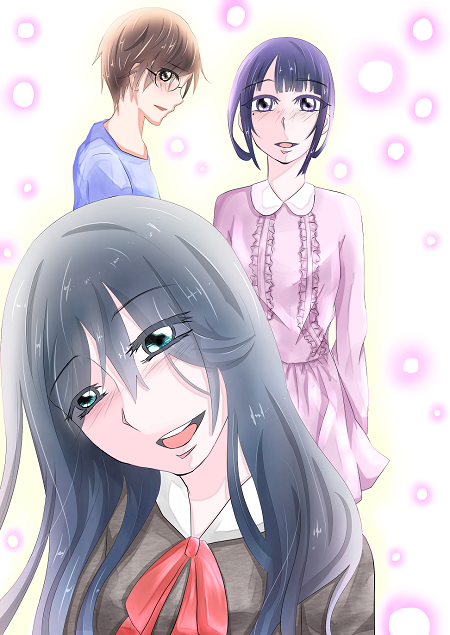
「紅葉ちゃん、凄い人気者だね」
「いつもこんな感じなのよ。どうしてかしら」
「紅葉が優しいからに決まってるでしょ!」
間を置かずに幸歌にそう断言されたが、あまり納得は出来なかった。飲み下せず、もやもやとした感覚を残す。
優しい? 私が?
こんな冷酷な私を、優しいと形容してみ良いものなのか。私より、幸歌や伸一の方が断然優しいと思うのだけれど。
私は思わず後ろを振り返ろうとする。だがその行動は、視界に飛び込んできた何色もの折鶴に阻まれた。
「……え?」
「お姉ちゃん、これあげる!」
差し出しながらニコニコと笑うのは、私がいつも担当をしている女の子だ。戸惑いながらも、それを受け取る。
「これ……、千羽鶴じゃない。どうしたの?」
「えへへ、みんなに手伝ってもらったの!」
体と羽のバランスが悪いもの、頭と尾が捻じれてしまっているもの……、形はけして綺麗とは言い難いものが多かったが、それらは間違いなく折り紙で出来た鶴だった。全く予想していなかったものを渡されたことに驚き、言葉を呑む。
一体、どれだけの時間をかけて折ってくれたのだろう。
……そして、一体何をこの子たちは祈ったのだろう。暑くもないのに、手のひらがじっとりと汗ばむ。声が震えそうになるのをなんとか堪えた。
「大変だったでしょう?」
「ううん、そんなこと無かったよ!」
「前にお姉ちゃんが折鶴の折り方を教えてくれたから、お礼に渡したかったんだ!」
「これで、きっと紅葉お姉ちゃんの脚も治るよね!!」
――――嗚呼。
私は静かに両目を閉じた。
子供たちの真っ直ぐで穢れの無い願い。他意など無い願い。
けれどこの両脚は、願ったところで治らないのだ。描いた夢は塗り潰されたのだ。
願っても、“無駄”なのだ……。
「……紅葉さん、ごめんなさい」
すると、重い足取りで奥から歩いてきた少女が、辛そうな表情で私に謝罪をしてきた。私より3つ年上の紀子さんだ。その向こうには、同じような顔をした中学生や高校生の人たちが立っている。
「私たちや先生たちが説明したのですが、分かってもらえなくて……」
「紀子ちゃん、どうして謝ってるの……?」
「そうだよ、別に悪いことはしてないでしょ?」
紀子さんや彼女の後ろの人たちの顔がますます暗くなっていく。私は、そんな紀子さんたちを安心させるように微笑みを作った。
誰も悪くない。悪くは無いのだ。
脚が治るようにと願った幼い子供たちも、理解させることが出来なかった紀子さんたちも。
「ありがとう、嬉しいわ。大切にするわね」
「本当? 部屋に飾ってくれる?」
「ええ、もちろんよ」
子供たちの頭を優しく撫でる。一体、どれほどの痛みをこの小さな体で受けたのだろう。一体、何度夜を泣いて過ごしたのだろう。
私には、推測することしか出来ない。実際に苦痛を受けた者にしか、理解など出来ない。
だから私は、せめて彼らを受け止める。それが、私に出来る最善のことだと信じているからだ。
「紅葉お姉ちゃんのこと大好きなの?」
後から様子を窺っていた幸歌が、そう子供たちに問いかけた。子供たちは少しも迷う素振りは見せず、
「うん! 大好き!」
「当たり前だろ!」
「紅葉お姉ちゃん、いつも色々な事教えてくれるもん!」
純粋な好意を一斉に向けられた。今まで経験したこともないそれらに、築き上げてきたあの決意が瞬間的にグラリと崩れそうになる。私は咄嗟に顔いっぱいに笑顔を張り付け、何とかそれに耐えた。
「ありがとう。……みんな、本当にありがとうね」
子供たちはエヘへと照れくさそうに笑う。先ほど千羽鶴を手渡してくれた女の子も、両の瞳を輝かせて言った。
「紅葉お姉ちゃん、どこにもいなくならないでね! 約束だよ」
「……ええ、もちろんよ」
どうか、掠れそうになった声に気付かれませんように。
*
私は神も運命も信じていない。
けれども、私が交わす約束とは真逆に突き進むように運命が出来ているのではないかと、本気で思えてくる。
……ここまで来ると、そう考えてしまうのは仕方がないというものではないか。
馬鹿馬鹿しいと一蹴出来なくなってくる。
その日、ゲームの世界はゲームでは無くなった。
憤怒、憎悪、悲嘆、畏怖、焦燥、自棄、絶望、後悔、困惑、諦念……、そんな負の感情が2つの世界を同時に覆い尽くしたのだ。あらゆる者がそれに飲み込まれ、衝撃のあまり言葉を忘れる人々が多くいた。
けれど私はその中でただ一人、笑っていた。周りからすれば、“狂気”として受け止められていたかもしれない。突き付けられた現実に狂ったのだと、そう考えた者もいただろう。
しかし、実際は全く違う。正反対だ。
――――歓喜。
“狂気”ではないのだ。もし言うのならば、“狂喜”であろう。
嗚呼、なんて素晴らしいことだろう!
嗚呼、この身を焦がすような喜びは何と言い表せばいいのだろう!
願いは完璧な形で叶ったのだ!
“もう一つの現実世界にしたい”……、これ以上の形で実現することなど不可能なはずだ。“もう一つの現実世界”を実現させるための策は、これの他には存在し得ないはずだ。
――――否、もう“もう一つの”ではない。この世界は、もはやニセモノではないのだ。
ここはすでに、唯一無二の現実なのだ!
この上なく完璧だった。言うことなど一つもない。
私には到底到達出来ない域にあったものを、彼は――――茅場晶彦はやり遂げてしまったのだ。
全身が震えた。
両手を胸に当て、ただ身を震わせた。背中がぎゅっと縮こまる。
私はひたすら愉悦に浸った。体の中が掻き回されているみたいに揺さぶられる。
こんな風に頭へどんどんと血が上り詰めていくような激しい感情は、覚えている限りの記憶を探っても見当たらない。
逆らうことはせず、感情に身を任せた。狂おしいほどの喜びに、湧き上がるこの世界への愛しさに。
……ああ、愛おしい。この世界が愛おしい。
私は笑っていた。
真っ赤な空を――――ローブを纏う巨大な死神を見上げ、笑っていた。
……笑っていた。
けれど、一つだけどうしても不可解なことがある。
頬に伝うこの涙は、一体誰のものなのだろうか?
感想を書く
この話の感想を書きましょう!
全て感想を見る:感想一覧
